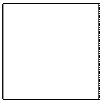���{�o�Ϙ_�Q�@�U�@���x�o�ϐ����P�@�@�i2014/10/27�j
�P�D���x�o�ϐ����Ɏ���܂Łi���K�ƕ⑫�j
�`�@�����v
���Ƒ̐��̕ύX�������@���v�@�匠�̏��݁F�V�c�������A�ے��V�c���A
��{�I�l���̏��F�A���ە����̉�����i�Ƃ��Ă̐푈�̕����A�O���������c�@���t��
�o�ω��v�@��O����̏�������F�J�����v�i�J���g���@�E�J�g�W�����@�E�J����@�j�A�_�n���v
��O����̏����Ȃ��F������́E�Ɛ�֎~
���̌�̌o�ϔ��W�Ƃ̊W
�푈�Ɛ�͂̕��������R�����{���畽�a���{�ւ̓]���ɂ���ċߗ׃A�W�A�Ƃ̍����������ɉł��A�f�Ղ̕����Ɗg�傪�\�ɂȂ����B�܂��A�R����c����}�����A���ꂾ���o�ϐ����ւ̓����𑝂₷���Ƃ��ł����B
�J���Ɣ_�n�̉��v�����������z�̕�������ʂ��č������v���g�債�Čo�ϐ����̊�b���ł߂�ƂƂ��ɁA�_�Y�������������߂ĊO�݂����R���E�@�B�E�Z�p�̗A���ɂ܂킷���Ƃ��ł����B
������́E�Ɛ�֎~���������͉�̂��ꂽ���A�Ɛ�֎~�͒��r���[�ɏI������B����ł��A�����I�ǐ��Ԃ����߁A�o�ϐ����𑣐i������ʂ��������B�܂��A���{�Ɓi����j�ł�������Ƒ����o�c����r������Čo�c�Ҏx�z�����܂����̂ŁA�ϋɓI�o�c�����₷���Ȃ����B
�a�@�o�ϕ���
��̐����]���O�FGHQ�́A��R�����i�R�����Y�\�͂̔��������w��ɂ��P�����܂ށj�ɏd�_��u���A�o�ϕ����͓��{���{�ɔC����B���C���t���́A�����s���ƒʉݖc���̗����Ɍ��������邪�A���������̕����i���Y�Ɖ^�A�E�ʐM�C���t���̉j��D�悹����Ȃ��B���{���{�́A�s�풼��̃C���t�������Z�ً}�[�u�ŗ}��������A�X�ΐ��Y�����Ő��Y���}�����A�f���R���̗A���s���Ȃǂɂ�萶�Y�͒x��A����ؓ���ˑ��̕����Z���z����ɑ��債�ăC���t�����ĔR�����B�����K���i�̕s��������J���^����_���^�����}���ɍ��܂��ċ��Y��`�҂�Љ��`�҂̉e�������܂����̂ŁAGHQ�͎Љ�^����}������ƂƂ��ɐH���E���i�𒆐S��GARIOA�������J�n�����B
��̐����]����F���̌����A�Ƃ��ɋɓ���̋ٔ��Ɛ�̉����ɂ��R����}���̂��߁A�A�����J�{�����{�́A�Γ��u�a�ƕČR��n�̈ێ�����ړI�Ƃ�����Ĉ��ۏ��̒����A����ѐ����R���͂̈�ɑg���ނ��߂̓��{�̍ČR���A�����đ��}�ȓ��{�̌o�ϕ����𒌂Ƃ��鐭������āA�o�ϕ����Ɋւ��Ă�EROA�����ɂ�镜�����ނ̊m�ہA�����̍팸��������̒�āA�o�ψ���9�����̎��{�Ȃǂ�i�߂��B���Y�ƃC���t�����É��������n�߂��Ƃ���ɋ}���ȃf�t������i�h�b�a�E���C���A�V���E�v�Ő��Ȃǁj�����{�����邪�A��ʂ̉��ق��Ɠ|�Y�����߂ɘJ���^���̗}�����K�v�ƂȂ�A���������瑈�c�����͂��D���A�������𗘗p���ċ��Y��`�҂��^������E����r�������B���̒���ɁA���N�푈�������N�����ꂽ�B���������h�b�W���C���ɂ��s���ƒ��N�푈�ɔ��������Љ��`���͂ւ̒e���ɂ���āA���{��`�I�ȘJ���W���Č������B
�b�@���N�푈�Ɠ��{�̍���������
�E���o��
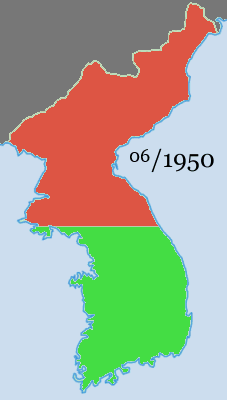 �@�j�R�g�������n�܂钆�ŁA1950�N6��25���ɒ��N�푈���u�������B�A�����J�͒����ɌR����������肵�čݓ��ČR���o��������ƂƂ��ɁA���A���ۗ��ɑi���ă\�A���Ȃ̉��ō��A�R�̔h�������肵�A���̑��i�ߊ��Ƀ}�b�J�[�T�[��C���i7��7���j�����B�����ɁA��p�E�t�B���s���E�C���h�V�i�ւ̌R���x�������������B�A�����J�̎Q��ɂ���čݓ��ČR��n�Ȃǂ��U�������\�������܂�A�}�b�J�[�T�[�͊C��ۈ����̋����ƌx�@�\�����̑g�D�𖽗߂����B�������A���A�R�i�؍��R���܂ށj�́A9�����߂ɂ͒��N������[�ɒǂ��l�߂�ꂽ�B9�����A���A�R�͔��������̐m��ւ̏㗤���ɐ��������B�}�b�J�[�T�[�́A�����R�̎Q���U������\��������̂Ŗk�i���T����ׂ��Ƃ̖{���̎w���ɂ�������炸�A����ɖk����w�߂��A���A�R��10�����{�܂łɒ����Ƃ̍����ɔ������B10��25���ɒ��ؐl�����a���`�E�R���勓���ĎQ�킵�A51�N���߂ɍ��A�R�͖k��38�x���t�߂܂ʼn����߂���A��i��ނ��J��Ԃ�����A�₪�Đ�����P�������B�}�b�J�[�T�[�͒����{�y�U����ƒf�Ō��\���Ėk��𖽗߂����̂ŁA�g���[�}���哝�̂͂��łɌ�����ۗL�����\�A�̎Q��ɂ��S�ʐ푈�ւ̔��W�����O���āA�}�b�J�[�T�[�i�ߊ��̒n�ʂ����C�����B51�N6���Ƀ\�A���x����Ă��A7������x������n�܂�������q�A�悤�₭53�N7��27���ɁA�k���N�R�E�����l���u��R�ƍ��A�R�̊Ԃŋx�틦�肪���ꂽ�B
�@�j�R�g�������n�܂钆�ŁA1950�N6��25���ɒ��N�푈���u�������B�A�����J�͒����ɌR����������肵�čݓ��ČR���o��������ƂƂ��ɁA���A���ۗ��ɑi���ă\�A���Ȃ̉��ō��A�R�̔h�������肵�A���̑��i�ߊ��Ƀ}�b�J�[�T�[��C���i7��7���j�����B�����ɁA��p�E�t�B���s���E�C���h�V�i�ւ̌R���x�������������B�A�����J�̎Q��ɂ���čݓ��ČR��n�Ȃǂ��U�������\�������܂�A�}�b�J�[�T�[�͊C��ۈ����̋����ƌx�@�\�����̑g�D�𖽗߂����B�������A���A�R�i�؍��R���܂ށj�́A9�����߂ɂ͒��N������[�ɒǂ��l�߂�ꂽ�B9�����A���A�R�͔��������̐m��ւ̏㗤���ɐ��������B�}�b�J�[�T�[�́A�����R�̎Q���U������\��������̂Ŗk�i���T����ׂ��Ƃ̖{���̎w���ɂ�������炸�A����ɖk����w�߂��A���A�R��10�����{�܂łɒ����Ƃ̍����ɔ������B10��25���ɒ��ؐl�����a���`�E�R���勓���ĎQ�킵�A51�N���߂ɍ��A�R�͖k��38�x���t�߂܂ʼn����߂���A��i��ނ��J��Ԃ�����A�₪�Đ�����P�������B�}�b�J�[�T�[�͒����{�y�U����ƒf�Ō��\���Ėk��𖽗߂����̂ŁA�g���[�}���哝�̂͂��łɌ�����ۗL�����\�A�̎Q��ɂ��S�ʐ푈�ւ̔��W�����O���āA�}�b�J�[�T�[�i�ߊ��̒n�ʂ����C�����B51�N6���Ƀ\�A���x����Ă��A7������x������n�܂�������q�A�悤�₭53�N7��27���ɁA�k���N�R�E�����l���u��R�ƍ��A�R�̊Ԃŋx�틦�肪���ꂽ�B
�@�푈�̋K�͂́A�肩�ł͂Ȃ����A�o�������S���K�͂̌R�������A�ČR�������������e�͑��풆�ɓ��{�ɓ����������e�ʂ̐��{�ɒB�����ƌ����Ă���B�R�l�̎����Ґ��́A�l�C��p���Ƃ��������`�E�R��k���N�R���S���l����Ƃ���A���A�R�����\���l�ɒB�����B�����������傫���ړ��������Ƃɉ����A�s�s�������J��Ԃ��������A�o�����X�p�C�E�Q�����̋^���A�R�ւ̔͂����ōٔ��Ȃ��ɑ�ʂ̏��Y�������̂ŁA���Ԑl�̎������S���l���͂邩�ɂ������B����ɂ��j��ɉ����A�ە���E���w������p�����A���̏e�e�͏d���������������炵���B�푈�́A�ň��̊��j��̈�B
�E�e��
�A�����J�@�h�~�m���_�������āA�Ƃ��ɃA�W�A�ł̐푈�ɉ�����A�g�債���B�����ɁA�P��I�ȌR�g���J�n���āA�R�Y�������iMilitary-Industry
Complex�j�̐����������炵���B����ɁA�Ɨ���������̋��A���n���𐼑��Ɏ�荞�ނ��߂̌o�ρE�R��������W�J�����B�����āA�A�����J�̍��ێ��x�͐푈���܂ފC�O�R���x�o�E�����̑��哙�ɂ��Ԏ������A�h���s���̐����e���̊O�ݏ��D�]���������A�A�����J�ۗL�̋����A�����J�h���̊C�O�c��������Ƃ����h����@�ւ̘H���蒅�����B
�\�@�@�A�@�X�^�[��������A�A�����J�Ƃ̌R�g�����Ɖ�������������ɐ[�������A���̕��S�̑���������āA�u�Љ��`�I�v�H�Ɖ�����ɂ���b�I�ȍH�Ɖ���B��������̍��������̍��x���ւ̓]�����x��Ă������B
�āE�\�̌R�g�����F�j�������~�T�C���i�F���J���ƕ��s�j�A���q�͐������c�₪�ēd�q���iElectronics�j�EICT�iInformation
Communication Technology�j����
���@�@�{�@�����iSpecial
Procurement�F��̔�ȊO�̕ČR�E���A�R�̑Γ������E�T�[�r�X�̒��B�A�h�������j�ƗA�o���ɂ��h�b�a�s�����������āu���N�����i�C�v�������炳�ꂽ���A�H�Ɛ��Y�\�͂��͂��߂Ƃ���o�ϓI�Ǝ㐫�i�G�l���M�[�E�^�A�E�ʐM�Ȃǂ̃C���t���j���I�悳��i�䑺�Ap.100-109�j�A�l�������O�݁i���O���h���j��p���āu�����������v��{�i���i�䑺�Ap.118-137�j�����B����ɁA����𐄐i����o�ϐ���E���x���������Ă������i�䑺�Ap.109-117�j�B
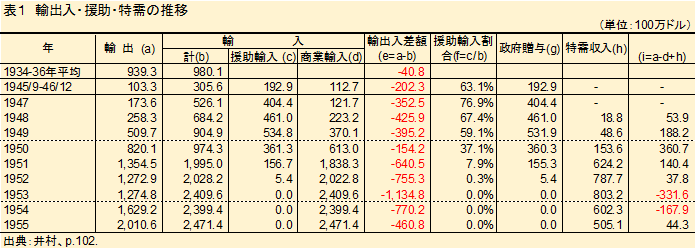
�E�����̓��e�F��Ƃ��Ēe��i�e�e�E�C�e�Ȃǁj���Y�Ǝ����ԁE�ʐM�@���̏C���@�ˁ@��Ɨ����ƊO�݂̑����ɉ����A�A�����J�Ƃ̋Z�p�i������̓I�ɔF�������ċZ�p�ړ]�E�����i�h����K�v�Ƃ���j����Ƃ���u�����������v���}�������B
�E�o�ϐ���E���x�̐����F���͂��O���ב֊Ǘ��ɉ����A�O���������x�i�����Y�ƕی�̋@�\���j�Ƃ��Ă��O���@�A�������������̐��i���{�J����s�A���{�A�o����s�A�������Z���A�u�a��ɂ����{�����M�p��s�E���{���Ƌ�s���j�A��Ƃ̎��{�~�ς̂��߂����ʏ��p���x�E�d�œ��ʌ��ƁA�Ɛ�֎~�@����i�s���J���e���E�������J���e���̖@�F�j�ȂǁB
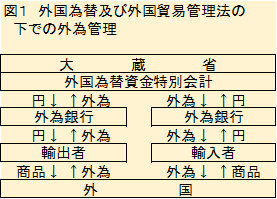 �@���t�Ɋt���R�c���u���ĊO�ݗ\�Z���쐬�B�O��v�ɏW�������O�݂��A�Y�Ɛ���i��ɐ헪�Y�Ƒ��Ƃ̈琬�ƕی�j�ƊO�ݏ����Ǘ��̊ϓ_����A�O�ݎ����������iFund
Allocation�j�Ǝ������F���iAutomatic Approval�j��2�g�ʼn^�p�����BFA���ł́C�i�ځE�ʉ݂ɉ����Ďg�p�\�ȊO�݊z�����蓖�Ă��C�i�ڂ��ƂɊ���������\�����B�A���\���҂͒ʎY�Ȃɂ��R�����C�O�݊����������ؖ�������t����C�������ɐ\�����ėA�������F�����B����C1950�N7-9�������瓱�����ꂽAA���ł́CAA�w��i�ڑS�̂̋��z�g�ƒʉݎw��͂��邪�C���͈͓̔��ł͎��R�ɗA���ł���B�A���\���҂͒��ڈ�ɐ\�����CAA�\�Z�c�g���Łu�����I�Ɂv���F�����̂����C���̗\�Z�c�z�ɂ��Ă��O�ݎ���̋����͈͂Ŋ����ɑ��z����邱�Ƃ����������B�i���|�C�g�u�������̊O�ݗ\�Z���x�v�w�����ٍ��ی����x�j
�@���t�Ɋt���R�c���u���ĊO�ݗ\�Z���쐬�B�O��v�ɏW�������O�݂��A�Y�Ɛ���i��ɐ헪�Y�Ƒ��Ƃ̈琬�ƕی�j�ƊO�ݏ����Ǘ��̊ϓ_����A�O�ݎ����������iFund
Allocation�j�Ǝ������F���iAutomatic Approval�j��2�g�ʼn^�p�����BFA���ł́C�i�ځE�ʉ݂ɉ����Ďg�p�\�ȊO�݊z�����蓖�Ă��C�i�ڂ��ƂɊ���������\�����B�A���\���҂͒ʎY�Ȃɂ��R�����C�O�݊����������ؖ�������t����C�������ɐ\�����ėA�������F�����B����C1950�N7-9�������瓱�����ꂽAA���ł́CAA�w��i�ڑS�̂̋��z�g�ƒʉݎw��͂��邪�C���͈͓̔��ł͎��R�ɗA���ł���B�A���\���҂͒��ڈ�ɐ\�����CAA�\�Z�c�g���Łu�����I�Ɂv���F�����̂����C���̗\�Z�c�z�ɂ��Ă��O�ݎ���̋����͈͂Ŋ����ɑ��z����邱�Ƃ����������B�i���|�C�g�u�������̊O�ݗ\�Z���x�v�w�����ٍ��ی����x�j
�E�u�����������v�F1950�N��̐��Y�Z�p���ǁE�v�V�̂��߂̓����B�����I�ɏd�_�Y�Ɓi�d�́F�Ύ吅�]���Ƒ�K�͉��ɂ���������A�S�|�F�����A�������A���D�F�����d�C�o�ڋZ�p�E�f�B�[�[���@�ւȂǁA�C�^�F���{������v�摢�D�j�ɏW���B�ΒY����Ζ��ւ̃G�l���M�[�]����A�d�@�E�����ԁE�����@�ہE���w�ł��B�@�ˁ@�o�ϊ�撡�A1956�N�̌o�ϔ����w���{�o�ς̐����Ƌߑ㉻�x�Łu���܂�o�ς̉ɂ�镂�g�͂͂قڎg���s�����ꂽ�B�c���͂���ł͂Ȃ��B�v�ƋL�q�B
�@�o�ϕ����Ɛ����̂��߂̌o�ϖ@�̌n�i�Ⴆ�ΊO���@��O�ז@�A��ƍ��������i�@�Ȃǁj��ݔ����������Z�����x�A��Ƃ̒~�ϑ��i�̂��߂̓��ʏ��p���x���d�œ��ʌ��Ɛ��x�Ȃǂ���������Ă������B����ɁA���N�푈�����ɂ��i�C�ɂ��O�݁iUS$�j�Ɗ�Ɨ������������A�d�_�Y�Ƃ��v��I�ɐ������鐭��̉��ŁA�A���Z�p�ɂ��ݔ����������i���ꂽ�B�܂��A���{�������u�o�ώ����܃J�N�v��v���i�֘A�����P�j���̌o�όv��̍�����s����B
�c�@���ہi�����ւ́j���A
1951�N06��31���A���ۘJ���@���iInternational Labour Organization : ILO�j�����A����Ȋw�����@���iUnited Nations Educational, Scientific and Cultural Organization : UNESCO�j�ɉ���
1951�N09��04���A���a���E���Ĉ��ۏ��
1952�N04��28���A���a����E��̉���
1952�N08��13���A���ےʉ݊���iInternational Monetary Fund : IMF�j�����ە����J����s�iInternational Bank for Reconstruction and Development : IBRD�j�ɉ���
1955�N09��10���A�ŋy�іf�ՂɊւ����ʋ����iGeneral Agreement on Tariffs and Trade : GATT�j�ɐ�������
�ˁ@���{�Ə��i�E�T�[�r�X�̍��ێ���̎��R���`�����ۂ�����B�������A�e���ʉ݂̑�US$�Œ胊���N�����ێ����Ėf�Ղ������������邽�߁A�ʉݓ��@�͗}������Ă����B
1956�N10��19���A���\�����Ɋւ��鋤���錾
1956�N12��18���A���ۘA���iThe United Nations�j����A���{�̉�����S���v�ŏ��F�B
�Q�D���x�o�ϐ����̓����̔c���@�@�ۑ�p����
�@GDP�iGross Domestic
Product�j�́A�o�ϊ����̌��ʐ��݂����ꂽ�e�t�����l�z�₻�̕��z�������������Ă���B�N����~�̑���CEO���玞�����S�~�̃A���o�C�g�܂ł��܂ށu�ٗp�ҏ����iCompensation
of employees�j�v�A�Œ莑�{�̌������p�����ł���u�Œ莑�{���Ձv�iConsumption of fixed capital�j�Ɩ@�l�����E���c�Ǝҏ����E���Y�����Ȃǂ��܂ށu�c�Ɨ]��iOperating surplus and mixed income�j�v�Ƃ�����Ƃւ̕��z�A����ɂ�����łł���u�ԐڐŁE�Łv�iIndirect tax / Taxes on production and imports�j�Ƃ������{�ւ̕��z�ł���B�������A���̋t�̐��{�����Ɠ��ւ́u�⏕���iSubsidies�j�v�́A���z����T�������B
�@GDE�iGross Domestic
Expenditure�j�́A��ɑe�t�����l���z��̎x�o���ŏI���v�̍\���������Ă���B�ŏI���v�Ƃ́A���{�o�Ϙ_�P�Ő��������Y�ƘA�֕\�ł����l�ł��邪�A�u����v�Ɓu�����v�i�ݔ��ƍɁj����сu�A�o�v��3�ɋ敪����A�x�o��̂��u���ԁv�Ɓu���{�v����сu�Z�ҁv�ɕ��ނ����B�ϋv������ł���u�Z��v�iDwelling�j��Љ�{�Ƃ��������ʁE�ʐM�E�G�l���M�[�E�h�Г��̎{�݂̌��݂́A�u�������Œ莑�{�`���v�iGross domestic fixed capital formation�j�Ɋ܂߂��Ă���B�u��Ɛݔ��v�iMachinery and equipment, Non-residential
investment�j�ւ̎x�o�܂�u�ݔ������v�́u���Œ莑�{�`���v�̒��S�I�ȓ��e�ł���A�ʏ�A���Y�\�͂̊g��������炷���̂ł���B�u�A�o�v�iExport�j�ɂ́A������E���{���̊O�ɒ��ԍ����܂܂�A�O���ɂ��w�����Ӗ�����B�u���A�o�v�iNet export�j�́A�f�Ս��z�iExport –
Import�j�ł���B
�@�e���ڂ̐��l�ω��̑��݊W�ɒ��ӂ��Ȃ����A�\�P���������悤�i���x�o�ϐ������ɏœ_�Ă�̂ŁA�ł��邾��68SNA�̐��l���g�����Ɓj�B�Ȃ��A1955-70�N�̉��ĂƂ̊ȒP�Ȕ�r�i���{�̐������̍����Ɩ��Ԋ�Ɛݔ������̑傫�����ۗ����Ă���B�j�́A�䑺�A�\3-1�y�ѕ\3-2�ip.154�j���Q�Ƃ̂��ƁB
�`�@���x�o�ϐ������i1955-73�N�j�̓����@�i���̐}�ɂ��e���ڂ̓������A����ȍ~�̎����Ɣ�r���Ă݂悤�B�j
���̂Q�}�́A�Бΐ��O���t�ł���A�c��������i�{���������Ȃ瓯���Ԋu�j�ƂȂ��Ă���B����āA�O���t�̌X�������Ȃ�Εω��������ƂȂ�B
�@�u�Ȃג�s���v�A�A�u�،��s���v�A�B�j�N�\���V���b�N�A�C��P���I�C���V���b�N�A�D��Q���I�C���V���b�N�A�E�v���U�����A
�F�o�u�������A�G����ň��グ�i3%��5%�j�E�A�W�A�ʉ݊�@�A�H����u�\�����v�v�J�n�A�I���[�}���V���b�N
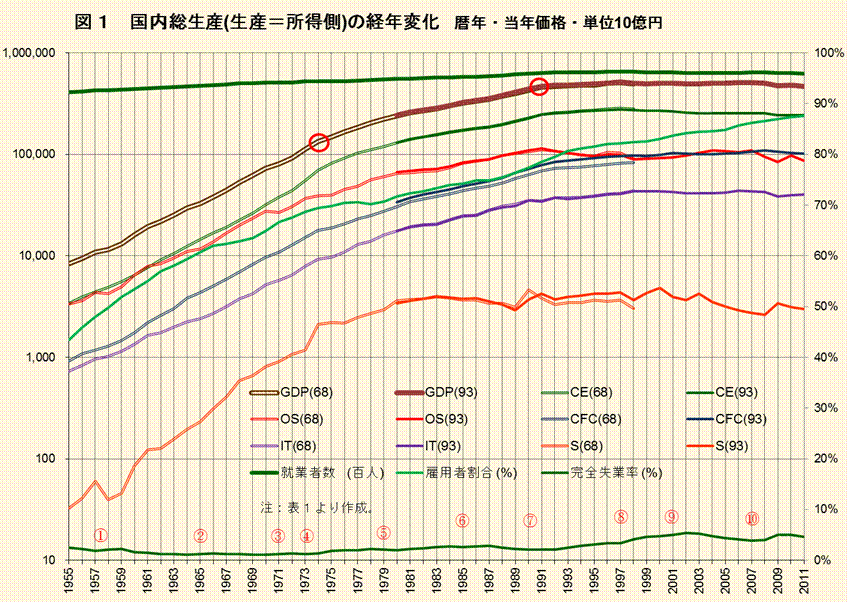
CE =
Compensation of employees�ٗp�ҏ����AOS = Operating surplus�c�Ɨ]��ACFC
= Consumption of
fixed capital�Œ莑�{���ՁA
IT = Indirect taxes�ԐڐŁAS = Subsidies�⏕���i�T�����ځj
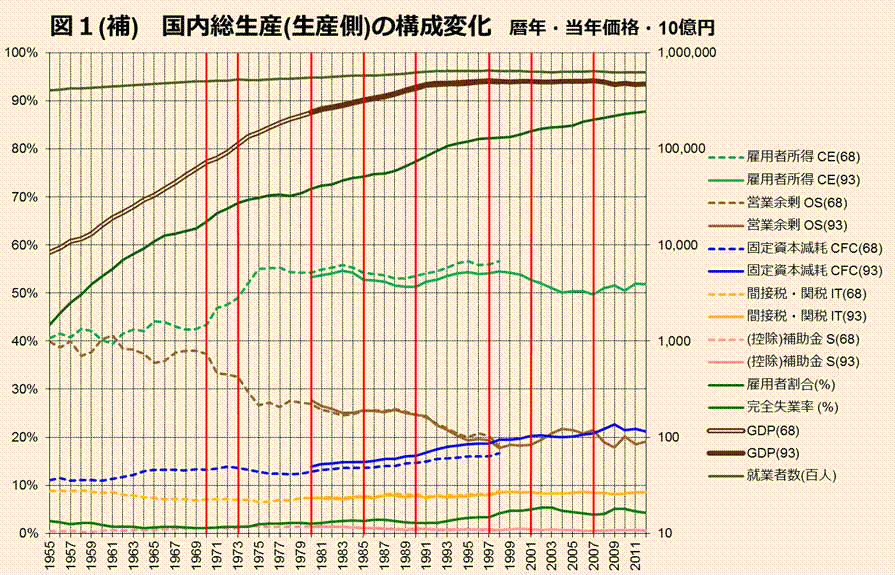
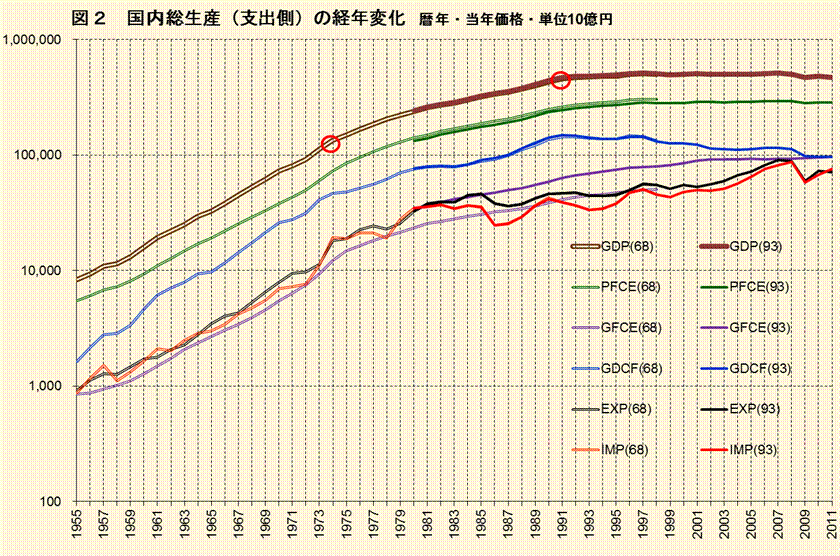
PFCE = Private final
consumption expenditure���ԍŏI����x�o�AAFCH = Actual final consumption of households�ƌv�����ŏI����A
GFCE =
Government final consumption expenditure���{�ŏI����x�o�AGAFC =
Government actual final consumption���{�����ŏI����A
GDFC = Gross
domestic fixed capital formation�������Œ莑�{�`���A
EXP= Exports of goods
and services���݁E�T�[�r�X�̗A�o�AIMP= Imports of goods and services���݁E�T�[�r�X�̗A���i�T�����ځj
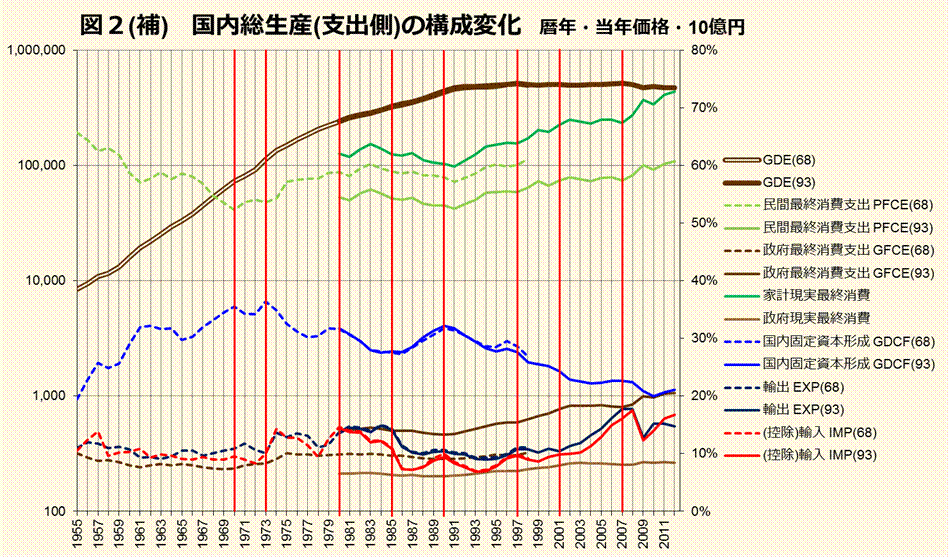
�Q�l�F�o�ϔ����@�t���������v�@����GDP�������Ɗ�^�x�i�l�����ʁj
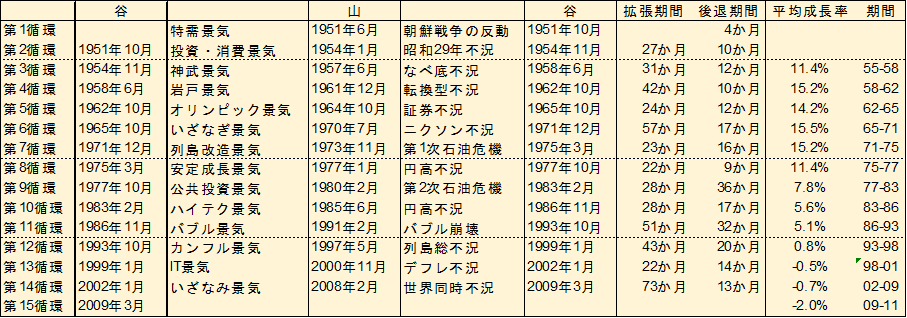
�a�@���x�o�ϐ������i1955-73�N�j�̊Ԃ̕ω�
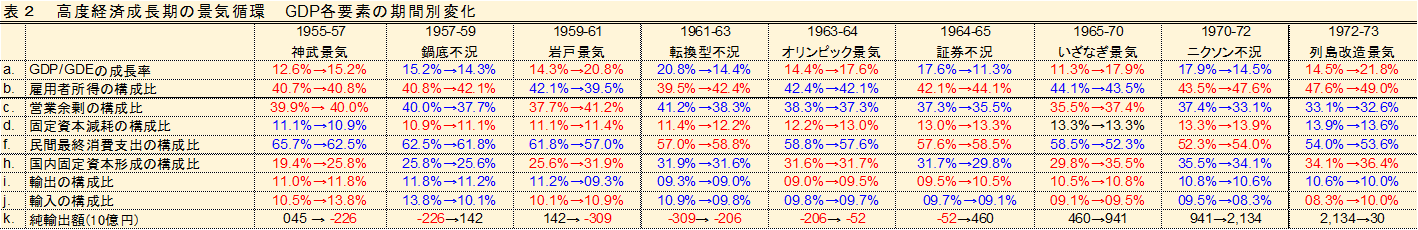
1956-57�N�F�_���i�C�A1959-61�N�F��ˌi�C�A1963-64�N�F�I�����s�b�N�i�C�A1964-65�N�F�،��s���A1966-70�N�F�����Ȃ��i�C
�b�@�����Œ莑�{�`���̓��e�̕ω��@�i�}�R����m�F���悤�j
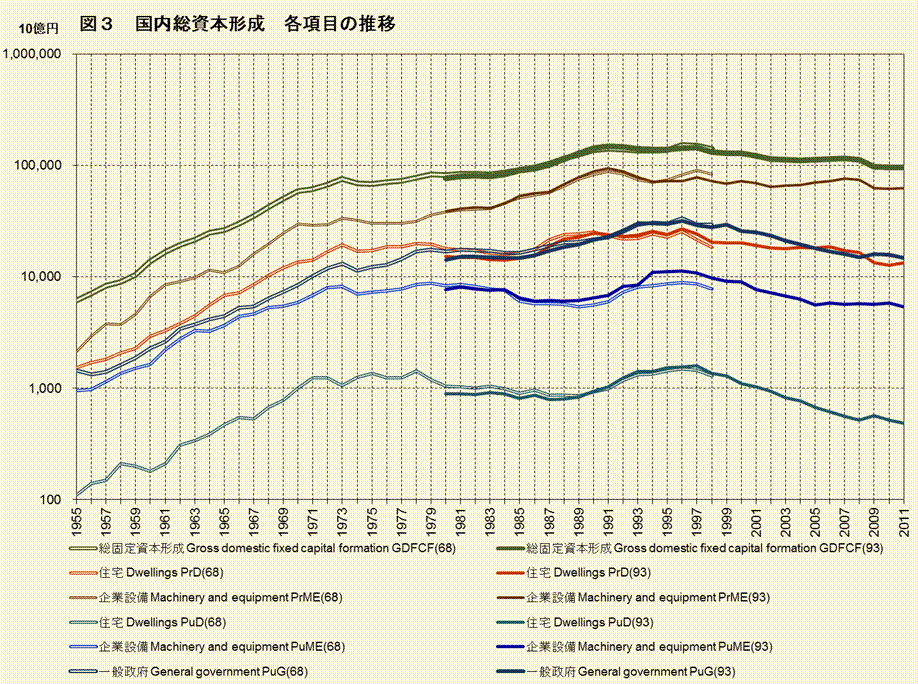
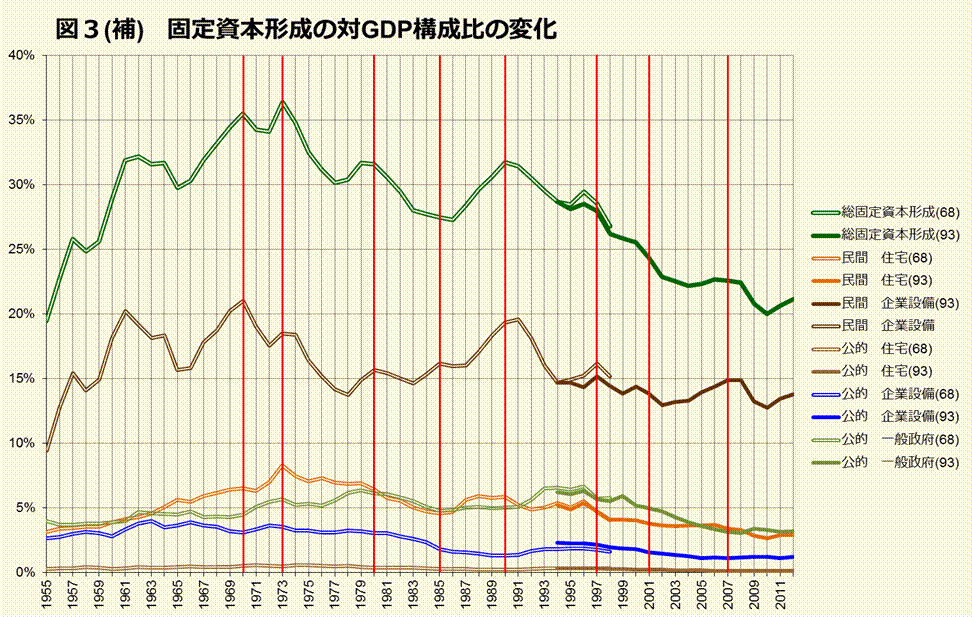
�@�����Œ莑�{�`���́A���Ԋ�Ɛݔ������E���ԏZ����A���{��Ɛݔ������i���c��ƂȂǁj�E��ʐ��{�����i���H�E�`�p�E��`�E�y�n�����E�����m�Ȃǁj�E���{�Z����ɕ�������B��Ɛݔ������́A���ړI�ɐ��Y�\�͂������グ�A���邢�͊��ۑS�ɖ𗧂B��ʐ��{�����̂����A�Ƃ��ɎY�Ɗ�Ր��������͊ԐړI�i��������̐v�����Ȃǁj�ɐ��Y�\�͂������グ����̂ŁA�i�C����ɂ��g�p����Ă����B�z�̑傫���ł́A���Ԋ�Ɛݔ����������ԏZ���or��ʐ��{���������{��Ɠ��������{�Z����̏��ɂȂ��Ă���B
�p�@�ȏ��O���ɂ����āA�܂��A�Бΐ��O���t�̓����܂��āA�}1�`�R����A�o�ϐ����̊e�i�K���邢�͌i�C�̊e�ǖʂŁA�ǂ̎x�o���ڂ��������x���Ă��������������Ȃ����B
1955-1970�F�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�A1970-1973�F�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�A1973-1980�F�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�A1980-1985�F�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�A
1985-1990�F�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�A1990-1997�F�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�A1997-2001�F�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�A2001-2007�F�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�B
�R�D�}���Ȍo�ύ\���ω��̈�v�����Z�p�����ɂ��Z�p�v�V
�@�}�S����A1955-73�N�A�Ƃ���1955-64�N�ł́A�����o�^�����ɂ�����O���l�䗦���������ł��������Ƃ��킩��B�o�^���ꂽ�O���l�̓������g�p����ɂ́A���̌������w�����A�K�v�ȋ@�ނ�A���Ȃ�����������K�v������B1964�N��IMF�W�����ւ̈ڍs�ɂ��f�ՂƎ��{�̎��R���̑O�́A���{���O�ݗ\�Z���x�̉��ŊO���בւ��Ǘ����Ă���A���̌�̎��R�����i�K�I�Ɏ��{���ꂽ�B���{�͊O���בւ̕����������ɂ��A�Z�p�������Ƃ��قڑ��ƂɌ��������A���Ƃ̊Ԃł͋ϓ��ɔF�߂��B���̌��ʁA���ƊԂł́u�ߓ������v�ƁA���ƁE������ƊԂ̊i�����`�����ꂽ�B�������A�������𗘗p������Ƃ́A�V�Z�p�E�V���Y�����ւ̓K����}�邽�߁A������Ƃ�I�ʂ��Ă��̏�ʊ�Ƃ��u�n��v����Ɉ����グ�A�o����Z�������A�Z�p�w���Ȃǂ��s�Ȃ����B�i�Q�l�F�������Y�i2008�j�u�������y�уT�v���C���[�E�V�X�e�������̌n���Ɖۑ��v�w�����ٌo�c�w�xVol.47,No.4,p.325-350�B�j
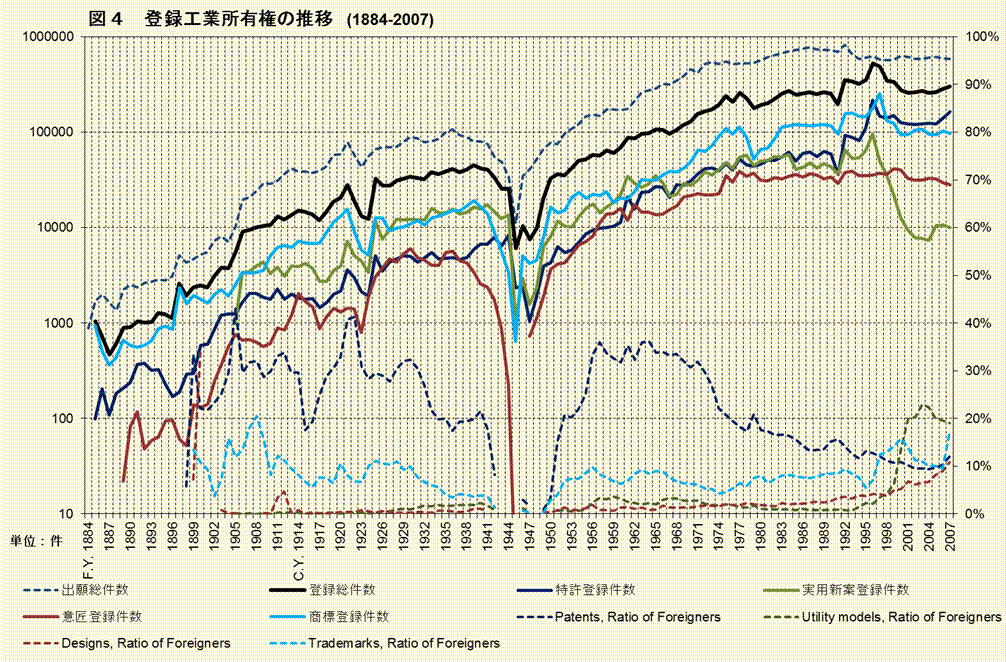
�S�D�A�o�̍��x��
�@���x�������ɂ́A�A�o�̕i�ڍ\�����傫���ω������B���̕\�i�\�S�j����A���̏�c�����悤�B
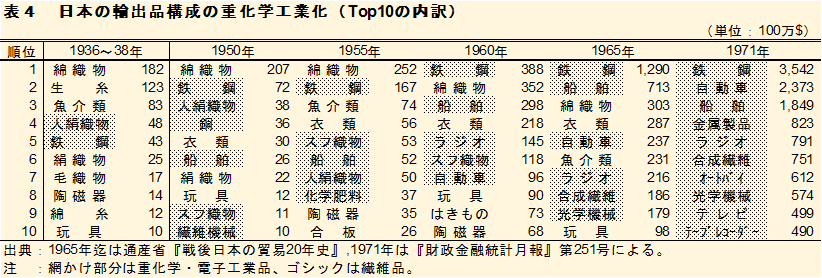
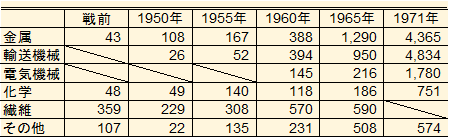
�T�D�V���ȍĐ��Y�\���̌`��
�@��O�̓��{�o�ς́A�n�吧�̉��ōk��_�Ƃ̏������}������ċ@�B���Ȃǂ̓����͐���A�܂����̒Ꮚ���ɋK�肳�ꂽ�����ɍ�����@�ۍH�ƓƐ�Ȃǂɂ��J���g���̖@�F���Ȃ��Ȃ��������߁A�J���҂��Ꮚ���ł������B����ɁA����n�ł͓y�n���Ǔ������i�݂ɂ����������B������J���Ɉˑ��������E�ȂȂǂ̑@�ۍH�Ƃ͋���ȍ��ۋ����͂��l���������A��O�̒Ꮚ���͉Ɠd�⎩���ԂȂǂ̑ϋv��������w������]�T��}�����A�q��̋��琅�������߂ɂ����A�d���w�H�Ƃւ̎��v�ƘJ���͋����Ƃ𐧖��B���̂��߁A�����s��ɂ����Ă����{���E���ԍ��ɂ������i�H�ƍ��Ƃ̋���������ŁA�f�Վ��x�̐Ԏ�����ԉ����Ă����B�i���̃C���[�W�����}���Ɏ����B�j
�@���x�o�ϐ������ɂ́A�o�όv��i�֘A�����P�E�R���u�o�ώ����܂��N�v��v���u���������{���v��v�Ȃǁj�Ɋ�Â������I�Ȍo�ϐ���Ƌ��͂Ȗf�ՁE�ב֓����̉��ŁA�d���w�H�Ƃ̑����̕��傪�A�u�f�ՁE�ב֎��R���v�i�֘A�����Q�́u�f�ՁE�O���ב֎��R���v���j�v���Q�Ɓj�܂łɍ��ۋ����͂��l�����邽�߁A�A���Z�p�Ɉˑ������ݔ�������i�߂��B�����̎Y�Ƃ́u�ߑ㉻�v�����łȂ��A�Ζ����w�┼���̂̂悤�ȐV���ȎY�Ƃ��n�o����A�A���Z�p�����p�����V���i�̊J��������ɍs��ꂽ�B�_�n���v�E�J�����v�ɂ���O�̏������㏸�����̂ŁA�ϋv������̎��v���g�債�ďd���w�H�Ɛ��i���v�������グ��ƂƂ��ɁA���w�������i�W���A�V�Z�p��o�c�v�V�ɂ��K���ł����N�J���͂̋������L�x�ƂȂ����B�܂��A�s��ɂ�镜���ƈ����g���ɉ����A�h�b�a���C���ɂ���ʉ��فE���Ƃɂ���ĉߏ�l�����������Ă����̂ŁA��K�͂Ȑݔ������ƌo�ϐ����ɂ��J���͎��v�̋}���ɂ��ւ�炸�A���Ȃ��Ƃ��O�����ł͒����㏸�͐��Y���㏸�ȉ��ɗ}����ꂽ�B���̍\���]�����܂ތo�ϐ����̌��ʁA�f�����ƔR���̗A���ˑ���[�߂Ȃ��玑�{���E���ԍ��̗A���ˑ�����E�p���Ă������B�i���̃C���[�W�����}�E�Ɏ����B�����ɂ̓R���s���[�^��IC�ȂǁA�Ȃ��A���Ɉˑ����镔���͎c�����B�j
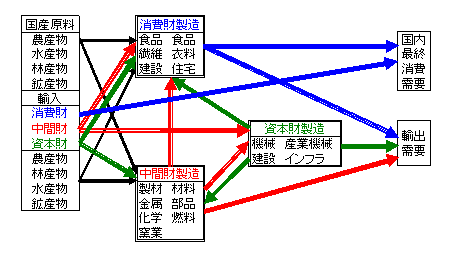 �@�@
�@�@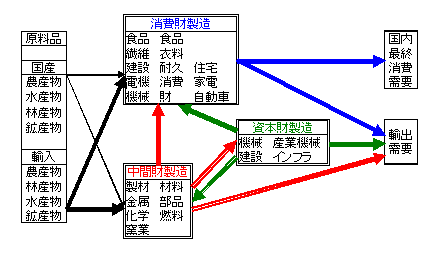
�U�D�������������Ăԁ|���x�o�ϐ������̓���
�@�u�������������Ăԁv�Ƃ����̔����ɂ́A�܂��A�u�����Ɓv�������i���ʒ��ߗ����j�𑝂₷���߂Ƃ��ɐV�s�ݔ����i�����j����ƁA
(1) �����W�ɂ���ē��Ƒ��Ђ����l�̐V�s�ݔ��̓�������������邱�Ɓi�g�y1�j
(2) ���̓������ށi�Y�Ƌ@�B�ނȂǁj�̔���������Ƃ��A����Y���邽�߂ɐV���Ȑݔ����������邱�Ɓi�g�y2�j
���K�v�ł��낤�B
�@�������A���̐ݔ��������A���ݔ���p����ꍇ�́A�������g�y1�͐����Ă��A�g�y2�͐�����B����āA�Z�p�J���\�͂��������ۋ����͂̂��鎑�{�����Y����i�������Y�Ƌ@�B�A�Ƃ��ɍH��@�B�j�������ɑ��݂��邱�Ƃ��A�܂��K�v�ȏ����ł���B
�@���̏�ŁA�����I�ݔ������ɂ�鎑�{�����v�̑������W���鎑�{��������Ƃ̐��Y�\�͂��邱�Ƃ������܂�A���̎��{��������Ƃ��ݔ��������s�����ƂŁA�g�y2����������i�ʓI�Ȕg�y2�j�B���邢�́A�ݔ��������Z�p�v�V���K�͉��Ȃǂ����̂ł��邽�ߊW���鎑�{��������Ƃ̊����ݔ��ł͂���ɑΉ��ł��Ȃ����Ƃ���A���̎��{��������Ƃł��Z�p�v�V���ݔ��������s���邱�ƂŁA�g�y2����������i���I�Ȕg�y2�j�B���ۂɂ́A�ݔ������͑啝�ȃR�X�g�_�E����V���ȗL�]�Y�Ƃ̑n�o���̂ŁA�����W�����݂������A���Ƒ��Ђɑ��āA���l�̂Ƃ�����������ȏ�̐ݔ��������������邩��A�g�y1���g�y2���Ĕ������邱�Ƃ����Ȃ��Ȃ��ł��낤�B
�@�ʏ�A�ݔ������͐��Y���̌�����̂ŁA���������Ƃ��ٗp�𑝂₷�Ƃ͌���Ȃ��B�������A�V���Ȑݔ������ɂ�苣���D�ʂ��m�ۂ����s��Ƃ́A���̗D�ʐ���ێ������Ă���Ԃɑ��Ђ����|���悤�Ƃ��āA�ٗp���g�債�����𑝂₷�ƍl������B��ǂ��̊�Ƃ��A���l�ł��낤�B����ɉ����āA�ݔ��̌��݂ɔ����ٗp�̑���������߂�̂ŁA���l������債�Ė��ԍŏI����x�o�������グ�邱�Ƃɂ��A��������Y����̐��Y���g�傷��i�g�y3�j�B�����̔g�y���e�Y�Ƃ��ꏄ���čŏ��́u�����Ɓv�������鐶�Y����ɂ��y�Ԃ��Ƃœ����g��̃��[�v���������A�X�p�C�����Ȍi�C�g�傪�N������B
���@�}�N���o�ϊw�́u�搔���ʁv�́A�lj��I�ȗL�����v�̑��傪���̑���ȏ�ɍ����������g�傷�邱�Ƃ��w�E���Ă���B�������A�����ł̖��́A�P�Ȃ�Input-Output�W�ł͂Ȃ��u�L�����v���������������v�̃��J�j�Y���ł���A���̊��W���Ȃ肽�����錻���̎d�g�݂ł���B
�@���̌i�C�g����ɂ́A���v�̑S�ʓI�Ȋg��ɂ�蕨���̏㏸�X�������܂�A�܂��z�����̈����グ�Ȃǂɂ���Ċ������㏸���A���i��L���،��ւ̓��@�̋@������傷��B�����ɁA�ٗp���g�債�ĉߏ�l�����z������Ă����ƁA�������㏸���A���ԍŏI������v������Ɋg�傷��ƂƂ��ɁA�������㏸�E�ێ��ւ̐����܂邪�A���@�ɂ�闘�v�ł�����J�o�[���邱�Ƃ͉\�ł���B�������A���i���@�́A���Y���i�̎��v�����̎����̌��E���z���Ċg�傳���A���Q����������B
�@�Ƃ���ŁA�ݔ����������̒��B���@�́A�������p�ϗ����Ȃǂ̓������ہi���Z���Y���Ƃ��ĉ^�p���j�̎������i���ȋ��Z�j�̂ق��ɁA�V���ȏo�����̒����i�����������邢�͑����j��Ѝ��s�Ƃ��������ڋ��Z�A����ɋ�s�ؓ��i�Ԑڋ��Z�j�Ȃǂ�����B�������p�ϗ������g���ꍇ�́A���p���Ԃ��o�߂����ݔ���V�������̂ɓ���ւ���u�X�V�v�����Əd�Ȃ�ꍇ������B�������A���Z���Y���̔��p�E�o�����̒����E�ؓ��̂�������s���������z�����邱�ƂɂȂ�̂ŁA�s�������������グ�鈳�͂ƂȂ�B�g�y1�`3�ɂ�苣���I�Ȑݔ��������Q������Ɠ����������v���Q�I�ƂȂ�B����ɐl����⌴�ޗ���̍�����������ĉ^�]�������v���g��A����ɓ��@�̂��߂̎������v���d�Ȃ��āA�s���������㏸�i�N���E�f�B���O�E�A�E�g�j���A�₪�ē��@������ċ��Q�����������Ă������ƂɂȂ�B
�@�ȏ�́A�ʏ�̍D�i�C�̔����ƉߔM���̃��J�j�Y���̈ꕔ�ł���B�܂�A�u�������������Ăԁv�Ƃ����o�ό��ۂ́A19���I�̌ÓT�I���{��`�ɂ�����10�N���x�̌i�C�z�̒��ł��A�s���E�o����D�i�C�ւ̓]���ƂƂ��Ɍ��ꂽ�B�S�ʓI�ȍD�i�C�́u�������������Ăԁv�ƁA�قړ��`�Ƃ�������B
�@�������A���x�o�ϐ������̓��{�ł́A�T�N���x���Z���Ԃ��D���E�s��������A�������d���w�H�Ƃ̑����̕���������ɏW�������ݔ��������s��ꂽ���Ƃ��A�d�v�ȓ����ł���B�ݔ������̏W�������i�����v���́A�f�ՂƎ��{�̎��R���ɂ��O����ƂƂ̋��������̗\�z�ł���B�Ƃ��ɁA���N�푈�����ŃA�����J�Ƃ̑傫�ȋZ�p�M���b�v�𑽂��̌o�c�҂�Z�p�҂��F���������Ƃ́A�A�����J���͂��߂Ƃ����O���Z�p�̓��������ɂ��ċZ�p�v�V���}�����邱�ƂɂȂ����B
�@�����ɁA���̊O���Z�p�̓������A�����I�ȁu�������������Ăԁv���ۂ��\�ɂ����v���ł�����B�܂�A����Z�p�J���ł́A�J���Ǘ��V�X�e���̉��P��R&D�����������B�\�͂̊g��A�����I�x���Ȃǂɂ���Ă��̊J�����Ԃ�Z�k���邱�Ƃ��\���Ƃ��Ă��A�Y�ƍ\����ς���قǂ̊v���I�ȋZ�p�v�V����ɐ��ݏo������������̂ł͂Ȃ��B�������A�O���ŊJ�����ꂽ�v���I�Z�p������������A�܂�Z�p�̌�i���ł���A��������邱�Ƃɂ���ďW���I�Ȑݔ������������邱�Ƃ��ł���̂ł���B
�@�������A�Z�p��i���������Β��ʂ���O�ݕs���̉��ł́A�O�݂𐭍��I�ɏd�_�Y�ƂɏW�������邽�߂��O�Ǘ����K�v�Ƃ���A���{�ł����{���ꂽ�B�Ȃ��A�ȊO�݂�p���ėA�������Z�p��ݔ��ɂ�鐻�i���ł��邾���A�o���ĊO�݂��҂��K�v������A�Z�p��ݔ��̗A���������R�X�g�Ő��Y����������Ȃ����߁A�����R�X�g�Ȃǂ̗}�����}����B���̂��߁A���ԍŏI����x�o�̊g�傪���������X�������邪�A�J�����v�Ŗ@�F���ꂽ�J���g�����u�t���v�����̒c�̌��E���c�ɂ�������������������グ�����A���Y���㏸�̐��ʂ̈ꕔ��J�����ɕ��z���������B�����āA�V��̕ۏ��Z��w���A�q��̋���Ȃǂ̂��߂̒��~��i�߁A�Ԑڋ��Z�ɂ�閯�Ԑݔ������̍��������������B����ɁA���x�o�ϐ������̓��{�ł́A�������鏤�i�̗A����O���̋�������ւ̒��ړ����ɂ��ẮA�O�Ǘ����O���K���ɂ���ēO��I�ɗ}�����āA���A���̎��R�����\�Ȍ���x�点�āA���v�������ɔg�y��������m�ۂ����B�A�o�s��ɂ��Ă��A����A�W�A�����ւ̐푈������o�ω������d���w�H�Ɛ��i�̗A�o�ƌ��т��A�J�Ă������B�������A�\4�Ɏ����悤�ɁA�A�o�i�\���̏d���w�H�Ɖ��ƍ��t�����l���͐��Y�̏d���w�H�Ɖ��ɒx��Ă���f�Վ��x�͐Ԏ���ł��������߁A1960�N�㔼�܂ł́A�i�C������������ƁA�A���������Ėf�Վ��x���Ԏ��ƂȂ�O�ݏ�������������̂ŁA�����x�o��}���������������グ�Đݔ�������}���A����ɂ���Či�C�����É����A�A�����}������ƂƂ��ɗA�o���v�J�i�߂��āA�f�Վ��x�����������O�ݏ���������Ƃ����A�����I�Ȍi�C�����i�u���ێ��x�̓V��v�j���s��ꂽ�B���ꂪ�i�C�z�̒Z���̏d�v�ȗv���̂ЂƂł������B
�@�܂��A�G�l���M�[��M���̋����E�����i���H�E�`�p�E�S���Ȃǁj�E���ʐM�Ƃ������C���t����Z����A�R�g�Ȃǂ̂��߂ɂ��Ƃ��ƕs�����Ă�����ɐ푈�Ŕj��A����ɉ����ċ}���ȑ�s�s�ւ̐l���ړ������������̂ŁA�}���Ȑ������K�v�Ƃ���Ă����B�Z��̋����������ς疯�ԕs���Y�Ǝ҂ɈςˁA�o�ϐ����ɂ��Ŏ��̑����Ɏx����ꂽ���{���ݓ������G�l���M�[�E��ʁE�ʐM�Ȃǂ̎Y�Ɗ�Ր����ɏW���������Ƃ́A���Ԑݔ������𑣂��A�o�ϑS�̂̐��Y���̏㏸�𑬂߂��B�����āA�o�ώ����܃J�N�v�������������{���v���j�̂悤�ȑ����I�o�όv��ɂ��o�ϐ����ڕW�̐ݒ�Ǝ{��̗��āE���\���A�ݔ������ӗ~���h�������B
�@��㖯�剻���v�ɂ���ď������z������������d�g�݂��������ꂽ���߂ɉƌv�̗]�T�����܂�A���w�����ɂ��J���͂̎��I����ƂƂ��ɁA�l���̓s�s�ւ̑�K�͂Ȉړ����j�Ƒ����݂��������Ƃ�A�����J���e���r�h���}�̕��f���A�����J�I�ȓd�������̃f�����X�g���[�V�����ƂȂ������Ƃ������A�Ɠd�⏬�`��p�ԂȂǂ̑ϋv������E���H�H�i�Ȃǂ̎��v�����N���A������Y�Ƃ̑��Ƃ��A���Z�p�����ɂ��đ��l�ȐV���i��V�Z�p���J�����Ă���ɉ����Ă������B
�@�������A�p���������ȂǁA���ւ̔z���͂قƂ�ǂȂ��ꂸ�A��K�͂Ȍ��Q�E���R�j���A�O������u�E�T�M�����v�Ɲ������ꂽ�u���E���E���́i�Ζ��n���牓�������̂ɍ��z�ȁj�v�Z��Ɓu�ʋΒn���v�Ȃǂ������炵�����Ƃ́A���L����K�v������B
�ۑ�F�@�i�P�j�@�ۑ�p�̉����A�N�V�����E�y�[�p�[�ɋL�����A29���i���j�܂łɌ������i12����4�K�a412�j�̃h�A���̃|�P�b�g�ɓ������Ȃ����B�@
�i�P�j�̐����ƉX��
�@�܂��A�}�P�`�R�͍����o�όv�Z�̐��Y�ʁi�e�t�����l�̕��z���ʁ������j�Ǝx�o�ʂ̒����ω���\�����̂ł���A�}�P����ѐ}�P�i��j�ŏ������z�̌X�������Ȃ���}�Q����ѐ}�Q�i��j�Ŏx�o�ʂ̎�v���ڂ̓�����ǂ��A����ɐ}�R�Ŏx�o���ڂ̒��̌Œ莑�{�`���̓��e�i���Ԋ�Ɛݔ��E���ԏZ��E���{��Ɛݔ��E���{�Z��E��ʐ��{�j��ǂݎ���Ă����悢�B�Ȃ��A�������哱�������ڂ́AGDP���z�ɑ��銄�������債�Ă��邱�ƂŔ��ʂł���̂ŁA�}�P�`�R�́i��j������̂������B���̌��ʂ́A���̂悤�ɂ܂Ƃ߂���B�i�@�j���́A�Œ莑�{�`�����Ő������哱�������ڂł���A98SNA�́u�ƌv�����ŏI����v�Ɓu���{�����ŏI����v�́A���ꂼ��68SNA�Ɠ��l�́u���ԏ���x�o�v�Ɓu���{����x�o�v�Ƃ��ĕ\�����B
|
1955-1970�F�Œ莑�{�`���i���Ԋ�Ɛݔ��{���ԏZ��A�O���͈�ʐ��{�{���I��Ɛݔ����j�A�㔼�ɂ͗A�o���A |
|
|
1970-1973�F���ԏ���x�o�{���{����x�o�A�i���ԏZ���{��ʐ��{�{���I��Ɛݔ��j |
|
|
1973-1980�F���ԏ���x�o�{�A�o�A�i��ʐ��{�j�A |
1980-1985�F���ԏ���x�o�{�A�o�A�i���Ԋ�Ɛݔ��j |
|
1985-1990�F�Œ莑�{�`���i���Ԋ�Ɛݔ��{���ԏZ��j�A |
1990-1997�F���ԏ���x�o�{���{����x�o�A�i��ʐ��{�{���I��Ɛݔ��j |
|
1997-2001�F���ԏ���x�o�{���{����x�o�A |
2001-2007�F�A�o�A�i���Ԋ�Ɛݔ��j�B |
�@���A�y�ɂ��̏́A�����ނˏ�L�̎�v���ڂ̈ꕔ�������Ă����B�������A�u�`�I�����ɒ�o���ꂽ�J�[�h�ɂ͋������A�������ɓ͂���ꂽ�J�[�h�ɂ͎�����v���i�x�o���ځj�̊m�F���Â����̂��������B�܂�A�ٗp�ҏ�����c�Ɨ]��Ȃǂ̐��Y�ʂ̍��ڂ����������̂�A�Y�ƕ��喼�Ȃ������i�������������̂��������B����ɁA�u�A���v���������҂����������A�����GDE�v�Z��̍T�����ڂł���A���A���v�ł͂Ȃ������̍��ڂł���B
�@�i�Q�j�@���x�o�ϐ����ɑ��ėA�o�͂ǂ̂悤�Ȗ������ʂ������̂��H�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�Q
�@�A�o�̑f�c�o��́A���x�����O���Ɍ������A�㔼�ɑ��債�Ă���B�܂��A�i�ڍ\�����A�\4�̂悤�ɂ��Ȃ�ω����Ă���B���̂悤�ȃf�[�^�܂��āA�l�@���ʂ������|�[�g�Ƃ���CHORUS�Ȃ���Blackboard�Œ�o���Ȃ����B������11��6���i�j�܂ŁB
�@�܂��A�A�o�Ƃ͊C�O�s��ւ̍��E�T�[�r�X�̔̔��ł���A�A�o�Ǝ҂͑Ή��Ƃ��ĊO���בցi���ےʉ��āj�����B�̔����A�o�ł���ɂ́A�܂��A���Y�s��̃j�[�Y���l�����Ȃ���Ȃ炸�A�i���E���i�̗��ʂł̍��ۋ����͂������Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�܂��A����n�悪�A���{����̗A����d���邾���̊O���בւ̊l���\�͂�L���邱�Ƃ��K�v�ł���B
�@���x�o�ϐ������̑O���ł́A�A�����J���u�O���בy�ъO���f�ՊǗ��@�v�ɂ�鋭�͂ȓ������~�̑h������ێ��ɕs�����ƔF�߂��悤�ɁAUS$1=\360�̈בփ��[�g�ł��A�܂����{�̖f�Վ��x�͕s����ł������B�Ƃ��ɁA�O�ׂ�������œ��肵���O���̋Z�p���v�@�B��p�����d�_�Y�Ƃ́A���̐������Ɠ��������Ő��i������R�X�g�͊����ɂȂ��ėA�o�����͂͊m�ۂł��Ȃ��̂ŁA���۔�r�ň����J���͂��K�v�ł������B����ɁA�������������A�����Đ����������́A�_��ŋ����n�悪���肳���̂ŁA���������ɋ������ꂽ�B���������āA���̋Z�p�����p��������A�o����ɂ́A���i����ѐ��@�̗����ł̗l�X�ȓƎ��̍H�v�iProduct Innovation & Process
Innovation�j���s���ł������B����āA�V�Z�p�̓���������ł����������ɂ͐V���i�̗A�o�͍���ł���A���̊ԂɊO�݂��l���������́A���łɍ��ۋ����͂��l�����Ă����y�H�ƕi�ł������B���Ȃ킿�A�A�o�́A�ݗ��Y�ƂɈˋ����āA�Z�p��A�����邽�߂̊O�݊l���ɍv�������̂ł���B�Ȃ��A�_�n���v��̔_�Ɛ��Y�͂̌���͐H���A����}�����A�l�������O�݂��d�v�Y�Ƃɉ]�͂��g�債���B
�@������J���͂���v�ȋ����͌��Ƃ��A����ɗA���Z�p���g�����Ȃ��Đ��i�̕i�������コ���A�Ǝ����i���J�����A���x�o�ϐ����̌���ɂȂ��ďd���w�H�Ɛ��i�̗A�o�����͂��l�����ꂽ�B�����A��ȗA�o��́A�푈�����i��Ɍo�ω����j�ŊJ�����E����A�W�A�ł���A���̒n�悪���{����̗A�����g�傷��ɂ́A���̒n�掩�̂̊O�݊l���\�͂Ɉˑ�����B���̊O�݊l���\�͂������̂��A�u�x�g�i�������v�ł������B�܂��A���{���R���i�Γ����ړ����̎��R�����O���@�Ȃǂ̋K���̊ɘa�E�P�p�j�̈��͂̉��ŁA�X�P�[�������b�g�̒Nj���i�߂��B�����A�A�����J�͌R���Y�ƗD��̋Z�p�J���Ƒ���Ƃ̑����Љ��ɂ���čݗ��d���w�H�Ƃ̍��ۋ����͂��ቺ�����̂ŁA���{�̑A�����J�f�Վ��x�������ɓ]�������B�������A���Y�\�͂��傫���g�債�č��������ł͎��v���s������Ɏ���A�A�o�͌o�ϊ����̈ێ��ɍP��I�ɕs���̎��v�ƂȂ��Ă������B
�@���̂��߁A������J���͂̌p���I�����͏d�v�ł��������A�}�����̌��ʂ��łɘJ���͕s�������݉����Ď��������̏㏸�X���������Ă����̂ŁA�J���Ǘ��̋����Ǝ��{�̐��Y���̈�w�̌��オ�}��ꂽ�B����ɁA���i�̉��H�x���グ�Ċ����i�i�ŏI���������ю��{���j�̗A�o�����͂̌��オ�A�R���s���[�^�����p���Đ��i����AProduct Innovation������ɐi�߂邱�ƂɂȂ����B
���@�֘A����
�����P�@�o�ώ����܃J�N�v���@�i1955.12.23�@�t�c����j
�@�o�ς̎�����B�����A�����傷��J���͐l���ɏ[���Ȍٗp�̋@���^����Ƃ������Ƃ́A�����킪���o�ςɉۂ����Ă���傫�ȉۑ�ł���B�o�ς̈�����ێ������̖����������邽�߂ɂ́A�����I�A���A�����ɂ킽��v����������A�l�y�ъ�Ƃ̑n�ӂ���Ƃ����o�ϑ̐��̂��ƂŁA�K�v�Ȍ��x�ɂ����ċK�����s�����ƂƂ��A�����S�ʂ̋��͂Čv��̖ڕW�ɑ������������ɑO�i���Ă䂩�˂Ȃ�Ȃ��B
�@���̂��߁A���a�O�ܔN�x��ڕW�N���Ƃ��āA���a�O��N�x�ȍ~�܃J�N�Ԃɂ킽��o�ώ����܃J�N�v������肵���B
�@�������Ȃ�����{�o�ςɂ����鏔���̂������̌v����Ԓ��ɂ͊��S�ȉ��������҂ł��Ȃ���������̂ŁA�����ɂ��Ă͂�蒷���I�Ȋϓ_�ɗ����ĕ�����u������̂Ƃ���B�܂��A�v��̖ڕW�����͕K�������Œ�I�Ȃ��̂Ƃ͍l�����A���̎����ɂ�����o�Ϗ�ɑ������e�͓I�ȉ^�p�ɓw�߂���̂Ƃ���B
�i�ڕW�j
�@����o�ς���Ƃ��Čo�ς̎����Ɗ��S�ٗp�̒B����}��B
�i�v����ԁj
�@���̌v��̊��Ԃ́A���a�O��N�x�����N�x�Ƃ����a�O�ܔN�x�Ɏ���܃J�N�ԂƂ���B
�i�O��j
�@���̌v�����̑O��Ƃ��āA���̏�������z�肷��B
��A���ې��ǂɂ͊�{�I�ȕω��͂Ȃ��B
��A���E�̐��Y����іf�Ղ͑Q���㏸���݂���̂Ƃ���B
�O�A�f�Ր����͎���Ɋɘa���邪�A�ʉ݂̎��R�������̉͊��S�Ȍ`�ł͊��҂���Ȃ��B�܂��A���E�̗A�o�����͌���������̂Ƃ���B
�l�A�K�b�g�����̉e���ł킪���ɑ���ł̈������������i��������̂Ƃ��邪�A�e���̎����Y�ƕی�̐���͈ˑR�Ƃ��đ����������̂Ƃ���B
�܁A�������͌v����Ԃ̑O���ɂ����ĉ�����������A���A����A�W�A�ɑ����i�����̉��������z�肵���n��Ƃ̖f�Ղ͊�����������̂Ƃ���B
�Z�A�����y�у\�A�Ƃ̖f�ՂɊւ��Ă͑Q�������I�����͊ɘa����A�o�ϖʂɂ�����킪���Ƃ̊W�����P�������̂Ƃ���B
���A���������͌v��̍ŏI�N���ɂ����Ă͊��҂��Ȃ����̂Ƃ���B
���A���s�̈בփ��[�g�̕ύX�͂��Ȃ����̂Ƃ���B
��A�����ɂ��Ă͋ɗ͈������̕��j���Ƃ�����̂Ƃ���B
�i�ȉ����ڂ̂f�ځj
�@�@��ꕔ�@�v��̓��e
�T�@�v��̕���
�U�@���������Y����ё��x�o
�V�@����ʂ̌v��
�@�@��@�v��B���̂��߂̕K�v�Ȏ{��
�T�@�z�H��
�U�@�_�ѐ��Y��
�V�@�f��
�W�@��ʒʐM
�X�@��������
�Y�@�Z���
�Z�@�����ٗp
�[�@�������Z
�����Q�@�f�ՁE�ב֎��R���v���j�@(1960. 6.24, �f�ՁE�ב֎��R�����i�t����c����)
�P�@���R���̊�{���j
�@�f�Ղ���шבւ̎��R���́A�h�l�e��K�b�g�̐��_�ɖ��炩�Ȃ悤�ɁA�e���̌o�ό𗬂������ɂ��A���E�o�ϑS�ʂ̔��W��}�邽�߂̊�{�I�ȕ����ł��邪�A�ŋ߂ł́A���E�o�ςɂ�����傫�ȗ���Ƃ��Đi�W���݂�Ɏ���A�킪���Ƃ��Ă��A���ێЉ�̈���Ƃ��āA�����鎩�R���̑吨�ɐϋɓI�ɏ������Ă䂭���Ƃ��̗v�ȏ�ɂȂ��Ă���B
�@�����ɖR�����l���̑����킪���o�ς����㒷���ɂ킽���Ĕ��W���邽�߂ɂ́A���E�̌o�ό𗬂̐i�W�ɑ������C�O�����Ƃ̎��R�Ȍ��Ղ���w�g�債�Ă䂭���Ƃ��s���̗v���ł���ƍl������̂ŁA���R�����ɗ͐��i���邱�Ƃ́A���E�o�ς̔��W�̂��߂̍��ۓI�v������݂̂Ȃ炸�A�킪���o�ώ��̂ɂƂ��āA����߂ďd�v�ȉۑ�ƂȂ��Ă���B
�@����܂ł킪���́A���̕����ƍ��ێ��x��̍���̂��߂ɁA�f�Ղ���шבւ̊Ǘ����s�Ȃ��Ă������A�������N�A���ێ��x�̍D�]�A�O�ݏ����̑����ɉ����āA�������̐������ɘa���A���R����i�߂Ă����̂ł���B�������čŋ߂̓��{�o�ς́A���̍����o�ϐ��������������̈���ƍ��ێ��x�̍�����̉��ɒB��������A����Ƃ��{���낵����A���x�����̎����Ƒ��܂��Ď��R��������ɐ��i��������̂Ɣ��f�����B
�@���̂悤�Ȏ��R���ւ̓��O�̏�ɂ��݁A���̍ہA�f�Ղ���шבւ̐�����ϋɓI�Ɋɘa���A�o�ύ������ɑ�������Ƃ̎���I�ȑn�ӂƐӔC����w�d�����邱�Ƃ́A�킪���o�ςɑ��đ����̍D�܂������ʂ����҂��邱�Ƃ��ł���B���Ȃ킿�A���R���ɂ��A�]���̊Ǘ������ɔ�����\����s�����͔r������A����ȊC�O���ޗ����̎��R�ȓ��肪��w�e�ՂƂȂ�A�Y�Ƃ̃R�X�g�͈����������A��Ƃ͍��ې����ɂ����鍇�����w�͂�v�������ȂǁA���R���͌o�ώ����̈�w�����I�ȗ��p���\�Ȃ炵�߁A�o�ς̑̎����P�𑣐i����ƂƂ��ɁA�L�������̐������e�̌���Ɋ�^���A�����Ă킪���o�ϑS�̗̂��v�i������̂ł���B
�@�������Ȃ���A���ۂɎ��R���𑣐i����ɓ����ẮA�܂����N�ɂ킽�蕕���I�o�ς̉��Ō`�����ꂽ�Y�ƌo�ςɋy�ڂ��ߓn�I�ȉe���ɏ\���l�����K�v������B�܂��킪���o�ς͐��������ƈقȂ�A�ߏ�A�ƂƂ���ɔ����_�ы��Ƃɂ������o�c����эL�͂ȕ���ɂ����钆����Ƃ̑��݂Ȃǂ̏��������A�܂��琬�ߒ��ɂ���Y�Ƃ��Ƃ̌o�c�A�Z�p��̎�_�ȂǑ����̖���L���Ă����ɁA�킪�����Ƃ�܂����ۊ��ɂ��Ă��A���B�����s��̂悤�Ȓ����I�Ɉ��肵�����͌o�ό���L���Ă��Ȃ����ƁA����т킪���ɑ��Ȃ����ʓI�ȗA�������[�u���Ƃ��Ă���Ⴊ�������ƂȂǂɂ��Ē��ӂ���K�v������B
�@���������āA���R���̐��i�ɂ������ẮA�킪���o�ς̓��ꐫ�ɑ���T�d�Ȕz�����A������ǂ����v��I�Ȏ��{��}����̂Ƃ��邪�A���R���͂킪���̒����ɂ킽��o�ϔ��W�̊�b���ł߂�d�v�ȕ���ł���̂ŁA�f�Ղ���шבւ̎��R���Ƃ���ɔ����o�ς̎��R�ȉ^�c���A�킪���o�ςɗ^����ϋɓI���_�ɑ����{�I�F���̉��ɁA���O�ɂ킽��o�ϐ���̓W�J�Ƒ��܂��āA��������͂ɐ��i������̂Ƃ���B
�Q�@���R���ɔ����o�ϐ���̊�{�I�����Ƒ�
1�@�o�ς̈����ێ������x������}��
2�@�ٗp�̊g��Ɨ���������ɓw�߂�
3�@�A�o�̊g��ƌo�ϋ��͂̐��i��}��
4�@���R���̐ϋɓI���_�����Y�ƍ\���̍��x���𐄐i����
5�@�_�ы��Ƃ̑̎����P����ђ�����Ƃ̋ߑ㉻�ɓw�߂�
6�@��Ƃ̑̎����P�̂��߂̊������ɓw�߂�
7�@�ŗ�����ѐ��x����������
�����R�@���������{���v��ɂ����@(1960.12.27 �t�c����)
�@���{�́A�ʍ��u���������{���v��v�����āA���a�O�\��N�\�\�����t�c����́u�V�����o�όv��v�ɑウ����̂Ƃ��邪�A����ɂ�����o�ς̉^�c�ɂ������ẮA���O�o�ς̎����ɉ����Ēe�͓I�ɑ[�u������̂Ƃ��A�Ƃ��ɕʎ��u���������{���v��̍\�z�v�ɂ����̂Ƃ���B
�@���������{���v��̍\�z
(1)�@�v��̖ړI
�@���������{���v��́C���₩�ɍ��������Y��{�����āC�ٗp�̑���ɂ�銮�S�ٗp�̒B�����͂���C�����̐���������啝�Ɉ����グ�邱�Ƃ�ړI�Ƃ�����̂łȂ���Ȃ�Ȃ��B���̏ꍇ�Ƃ��ɔ_�ƂƔ�_�ƊԁC���Ƃƒ�����ƊԁC�n�摊�݊ԂȂ�тɏ����K�w�Ԃɑ��݂��鐶���エ��я�����̊i���̐����ɂƂ߁C�����č����o�ςƍ��������̋ύt���锭�W�������Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
(2)�@�v��̖ڕW
�@���������{���v��́C����10�N�ȓ��ɍ��������Y26���~�i33�N�x���i�j�ɓ��B���邱�Ƃ�ڕW�Ƃ��邪�C�����B�����邽�߁C�v��̑O�����ɂ����āC�Z�p�v�V�̋}���Ȑi�W�C�L�x�ȘJ���͂̑��݂Ȃǐ������x���邫��߂ċ����v���̑��݂ɂ��݁C�K�Ȑ���̉^�c�ƍ����e�ʂ̋��͂ɂ��v�擖��3���N�ɂ���35�N�x13��6,000���~�i33�N�x���i13���~�j����N����9%�̌o�ϐ�����B�����C���a38�N�x��17��6,000���~�i35�N�x���i�j�̎�����������B
(3)�@�v���Ƃ��ɗ��ӂ��ׂ����_�Ƃ��̑�̕���
�@�o�ϐR�c��̓��\�̌v��́C����d���ׂ����_�Ƃ��̑�̕����͂��Ƃ��C���̑����ʂ̏�ɉ����C�e�͓I�ɑ[�u����ƂƂ��ɁC�o�ς̎��Ԃɑ����āC�O���v��̖ړI�ɕ����悤�{����s��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�Ƃ��ɂ��̏ꍇ���̏��_�̎{��Ɉ⊶�Ȃ�����������̂Ƃ���B
(�)�@�_�Ƌߑ㉻�̐��i
�@�����o�ς̋ύt���锭�W���m�ۂ��邽�߁A�_�Ƃ̐��Y�A�����y�э\�����̊e�ʂ̎{��ɂ킽��V���Ȃ锲�{�I�_���̊��ƂȂ�_�Ɗ�{�@�𐧒肵�Ĕ_�Ƃ̋ߑ㉻�𐄐i����B
�@����ɔ����_�Ɛ��Y��Ր����̂��߂̓����ƂƂ��ɁA�_�Ƃ̋ߑ㉻���i�ɏ��v���铊�Z���z�́A�����ϋɓI�Ɋm�ۂ�����̂Ƃ���B
�@�Ȃ��A�����Ƃ̐U���ɂ��Ă��E�Ɠ��l�ɑ[�u������̂Ƃ���B
(�)�@������Ƃ̋ߑ㉻
�@������Ƃ̐��Y�������߁A��d�\���̊ɘa�ƁA��ƊԊi���̐������͂��邽�߁A�e�ʂ̎{������͂ɐ��i����ƂƂ��ɂƂ��ɒ�����Ƌߑ㉻�����̓K���ȋ������m�ۂ�����̂Ƃ���B
(�)�@��i�n��̊J�����i
�@��i���̋����n��i���B�A����B�A�R�A�A�l���암�����܂ށB�j�̊J�����i�Ȃ�тɏ����i�������̂��߁A���₩�ɍ��y�����J���v������肵�A���̎����̊J���ɂƂ߂�B����ɁA�Ő����Z�A���������⏕�����ɂ��ē��i�̑[�u���u����ƂƂ��ɏ��v�̗��@���������A�����n��ɓK�������H�Ɠ��̕��U���͂���A�Ȃ��Ēn��Z���̕�������Ƃ��̒n��̌�i��������B��������̂Ƃ���B
(�)�@�Y�Ƃ̓K���z�u�̐��i�ƌ��������̒n��ʔz���̍Č���
�@�Y�Ƃ̓K���z�u�ɂ������ẮA�킪���̍��x�������ɂ킽���Ď������A��Ƃ̍��ۋ����͂��������A�Љ�{�̌��������߂邽�߂Ɍo�ύ������d���Ă䂭���Ƃ͂��Ƃ��K�v�ł��邪�A���ꂪ�n�摊�݊Ԃ̊i���̊g��������炷���̂ł��Ă͂Ȃ�Ȃ��B
�@�������āA�o�ύ������d���A�����ɒn��i���̊g���h�~���邽�߁A�Ƃ��ɒn��ʂ̌��������ɂ��ẮA�n��̓����ɏ]���ē��Z���̔�d��e�͓I�ɒ�������K�v������B����ɂ��o�ϔ��W�ɑ����������������̌��ʂ����߂�ƂƂ��ɁA�n��Ԋi���̐����Ɏ�������̂Ƃ���B
(�)�@���E�o�ς̔��W�ɑ���ϋɓI����
�@���Y������ɂ��ƂÂ��A�o�����͂̋����Ƃ���ɂ��A�o�g��A�O�ݎ����̑��傪�A���̌v��̒B���̏d�v�Ȍ��ł��邱�Ƃɂ��݁A���͂ȗA�o�U����Ȃ�тɊό��A�C�^���̑��f�ՊO������������u����ƂƂ��ɁA��J�������̌o�ϔ��W�𑣐i���A���̏������������߂邽�߁A�L���e���Ƃ̌o�ϋ��͂�ϋɓI�ɑ��i������̂Ƃ���B
�i�ʍ��@���ڂ̂f�ځj
�@�@��ꕔ�@����
�T�@�v��쐬�̊�{�I�ԓx
�U�@�v��̉ۑ�
�V�@�ڕW�N���ɂ�����o�ϋK�͂ƍ\��
�@�@��@���{��������̌v��
�T�@�v��ɂ����鐭�{�̖���
�U�@�Љ�{�̏[��
�V�@�l�I�\�͂̌���ƉȊw�Z�p�̐U��
�W�@�Љ�ۏ�̏[���ƎЉ���̌���
�X�@�������Z�̓K���ȉ^�c
�@�@��O���@���ԕ���̗\���ƗU������
�T�@���ԕ���̒n��
�U�@�f�Ղ���ьo�ϋ��͂̑��i
�V�@�Y�ƍ\���̍��x���Ɠ�d�\���̊ɘa
�@�@��l���@���������̏���
�T�@�ٗp�̋ߑ㉻
�U�@������̌���ƍ��x��
�V�@���������̏���