[total]
八王子の私立大学教授による盗作例
春風社
Home |
補遺 1 | 補遺 2
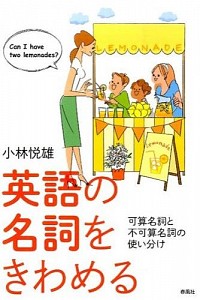
県職員:分かりません。。。。ひとつ忠告しましょう。あなたは自分でしたことに責任を持たなくてはいけない。自分でしたことは自分であると分かれば、そのようなことに惑わされず、気持ちが楽な生き方ができます。もう私に電話しないでください。
この人物は農地整備の専門家ですから、私の畑が14年以上も置かれて来た状況を私よりも早く理解していたのだと思います。
この二日前、2018年2月7日(水)の午後4時半ころ、合同庁舎のこの課を訪れて、話を聞いてもらって、説明を求めた時に聞いた「馬入れ」ということばから、その晩、私もどうしてこのような状況が生まれたのかを15年ぶりに思い出すことができました。
彼は言っても大丈夫だという事実だけを述べて、なぜか真実味のない響きと表情をしていましたので、不信感で顔を見ることはしませんでした。嘘は言っていないが、本当のことを隠している。そういう響きです。
なぜそんな大きな声でみんなに聞こえるように話すのだろう。課のひとたちに聞いてもらいたいのだろう。そして課長に認めてもらって昇進したいのだろうか。
名札を見ると、それを手で隠すのです。そんなの隠さなくても合同庁舎の入口にちゃんと名前が出ています。なぜ私は彼が私を丸め込もうとしたと直感したのでしょう。そうした仕草とから分かったのでしょう。
しかし、彼の語った事実の断片がヒントになって、その夜、すなわち2018年2月7日の夜、私の陥ったいきさつが15年ぶりに思い出されてきました。それまでは、公図と現場だけしか見ていなかったのです。現場だけ見ていても何かおかしいことが起こっているのかどのように証明したらよいか分かりませんでした。仕事も忙しい。2017年9月頃、市役所に行って相談した所、まず、登記所に行って登記簿を見て面積を確認したらというアドバイスを受けました。登記簿を取ることによってようやく具体的な数字が現れてきたのです。それについては後ほど詳述したいと思います。
「馬入れ」こそなかったのですが、北側から私の畑に入ることができるから、改良区対象としなくてもよいので、現況のまま残すという事情があったことを思い出し、うれしくなってこの担当者に電話したのですが、真実を見せなくしようとする敵に情報を与えてしまったのです。結果的には、私の畑は最初はそういう事情で現況のままに残されたのですが、ある時点で、改良事業に加わると今の形の悪い畑を使いやすく整備できるから、改良事業に加わったらという話と新子田団地に土地の一部を売却するという話に納得して、ハンコを押しました。
このことは最初思い出していなくて、私は改良事業から除外されているはずだと主張していましたので、わたしの間違いです。
この点については、嘘を言ったつもりはないのですが、その時点では、「新子田団地に売却などしていない」と強く言いましたので、これについては、わたしの間違いです。
私は正直に生きたいといつも思っています。正直に生きることは時に本当のことを言い続けなければいけないので、気持ちが楽にならないことがあります。特に自分の主張と相手の主張が違う場合はとても苦労をします。相手だって自分が間違っているなどとたやすく認めたくないからです。
相手にも正直を求めることが正しいと言っても、それが相手にとって不利なことなら、素直に認めないでしょう。
もちろん、私は嘘をつかない、とは言えない。義務でない集まりに行きたくない時に、体調不良だとか、急用ができたなどの嘘をつきます。行きたくないから行かないと言えない場合もあります。それはまた別のお話です。
自分の行動に責任をもつ、自分の取った行動が結果に関わる、というのは一面的な考えです。その自分の取った行動は本当に自分だけの判断だったのか。もしそうなら世間に詐欺事件などない。
自分の行動とその結果について責任を持つというこの人物は「泣き寝入り」を人に強いて来たのでしょう。
自分自身を納得させることは必要です。納得できないこともあるからこの世には裁判があるのです。自分をごまかして納得することはこの人物には楽なのでしょう。そうやって生きてきたから真実などどうでもよいのでしょう。誰かに言われたことをあたかもすぐれた哲学的考えだと思って、難しい仕事を避けてきた結果の公務員なのでしょう。かれは面倒な仕事がしたくないのです。ひとの悩みなど、その人に責任を取らせるようにしむけて、自分にいやな役目が回って来ないようにしさえすればどうでもよいのです。黒沢明の「生きる」を見るとよいでしょう。
自分の行動や選択が嘘の情報に基づくこともあります。さまざまな条件によって、自身の行動の結果が本当に自身の責任と結びつくのかどうかが問われることをいつも頭に置かなくてはいけない。極端な例を言いましょう。道を歩いていた子供が金槌で頭を殴られて殺された事件が昔ありました。この子供の死は自己責任なのか。お前がその道を通ったから殺されたと言えるのか。言える訳はない。しっかりした判断ができない子供でなくて一人前の大人だったらそういえるのか。駅でいきなり刺された大人もいます。すべて結果というのは自分の行動のために起きたのだろうか。原因結果には本人だけでなく、他者が関わるという事実を落としている似非哲学だ。
また、この人物の発言には事実を隠蔽しようとする本当の目的が隠されています。専門家が正義を忘れた例です。公務員が自己保存を企んでいます。いやな仕事から逃げようとしています。
この件に関する「各筆換地等証明書」という書類は私の分は手に入れたのですが、となりの畑の人のものは証拠隠滅のために処分してしまうかもしれません。処分はできないかもしれませんが、隠して公表しないでしょう。この人ならやりかねない。
|
All rights reserved by Etsuo Kobyashi: since Feburary 11h, 2018 [total] 八王子の私立大学教授による盗作例 |
Amazon 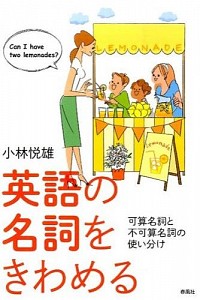
|