あるいは、環境コミュニケーション専攻への、ブリリアントな論文を仕上げるための人類学からのささやかなメッセージ
第1回研究会(2008.12.20).
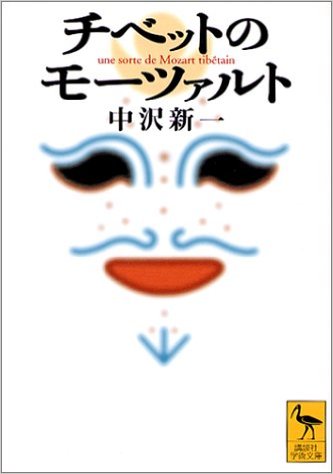
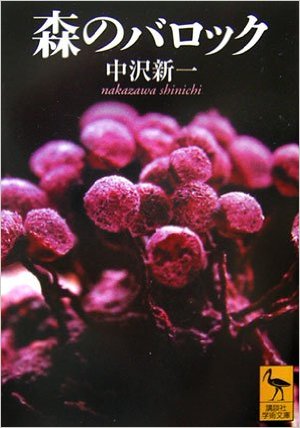


『チベットのモーツァルト』(以下、チベモツ)の文庫版の「まえがき」において、中沢さんは、「チベモツ」を、古典的な古い時代に、人間はどのような精神(心)をもち、何を考えていたのかを知るための「精神(心)の考古学」であると評した吉本隆明のことばを、当を得たものとして引いた上で、自分自身は、マルクス、フロイト、レヴィ=ストロースの影響の下に出発したが、人類学や民俗学によって取り扱われてきた対象の「奥にはいっさいの近代的な分析の道具を拒絶する、堅い岩盤のようなものが存在している」ことに気づき、言語同断な地層を掘り返す作業に乗り出したのだと述べている。それは、2,300年の厚みしかない「近代」を掘り返すフーコーの「知の考古学」を超えた「意識(心)の考古学」とでもいうべき試みだったのだという。
次に、『雪片曲線論』の「あとがき」(1984年のクリスマスの日付)において、中沢さんは、それを、チベモツと『森のバロック』の中間的な書物であると位置づけた上で、じつに、驚くべき先見を語っている。彼の考えでは、フーコーやクリフォード以降の学問では、モダンな批評理論がその限界点にまで立ち向かったのだけれども、その先の一歩を踏み出すことの危険性の前にたじろいだまま、思考のポジティヴィズムという名の保守主義へと立ち戻っている。『雪片曲線論』は、はっきりとそれらから身を引き剥がすための書物であるという。うーん、いままさに、人類学で起こっていることは、これではないか。モダンな批評理論の先の新保守主義。これらは、ともどもに切り裂いてゆかねばならないのではないかという思いを、わたしは新たにした。
Nさんは、その後、中沢さんが、『森のバロック』を執筆し、粘菌のなかに、生きているのでも死んでいるのでもなく、動物でも植物でもない、原初における「流動的なもの」を嗅ぎつけた南方熊楠のなかに、後の『対称性人類学』へといたる足取りを見出したことを指摘した。研究会発表で、Nさんは、『対称性人類学』から、とりわけ、仏教をピックアップした。一神教的、資本主義的、科学合理主義的、ヨーロッパ的な思考の基底には、神話的世界、ドリームタイム、対称性無意識という名称で変奏して奏でられる、ヒトの心の基底をなす思考がある。ヨーロッパは、そのような対称性無意識を抑圧して自己成型したのである。対称性無意識とは、野生の思考にほかならないが、いわゆる前近代社会の野生の思考だけでは、ヨーロッパ的な思考が含みもつ、非対称を生み出してしまう思考に立ち向かうことはできない。その意味で、野生の思考を、自己の鍛錬の技法にまで高めた仏教という知恵を用いなければならないのである。
第3回研究会(2009年1月20日)
第4回研究会(2009年3月31日)
中沢新一「華やぐ子午線」『雪片曲線論』所収
自然哲学とは何か?その起源は、ギリシャ哲学のイデア論にまで遡ることができる。ギリシャ哲学は、自然を、能産的な(自然成長性をもつ)ものとして見るそれ 以前の「古代の哲学」から身を引き剥がし、人間が自然を飼い慣らすために、言語による秩序化をつうじて、「自然哲学」を生み出した。その哲学の流れは、や がて、キリスト教神学を深く組み入れながら、ルネサンス期のデカルトを経て、カントの後、ヘーゲルによって、精神現象学のなかで、弁証法的なロジックをつ うじて、完成されていった。ヘーゲル哲学が、正・反のあるいは主・奴の弁証法から組み立てられることが重要なのは、それが、それ以降の近代的自我の形成に 大きな影響を与えただけでなく、現代のわたしたちの暮らしに、無視することのできない甚大なる影響を与え続けているからである。ヘーゲル的な自然哲学に は、自己である主=文化が、他者である奴=自然に対して、その覇権を打ち立てるという基本原理がある。他方で、ニーチェ、ハイデガーからフーコー、ドゥ ルーズ、デリダへと連なるディオニソス的な哲学の系譜では、プラトンからヘーゲルに至る歴史において継承・発展させられてきた、アポロン的な哲学を転倒させる試みが行われてきた。
ところが、ニーチェ以前にも、ソクラテス=プラトン以前の自然哲学へと遡及する試みがあった。それが、17世紀 のスピノザとライプニッツの哲学である。スピノザは、そのようにして、ドゥルーズによって、再発見されたのである。スピノザとライプニッツは、顕微鏡を発 明したレーウェンフークと同時代人であった。顕微鏡の発明は、スピノザとライプニッツの哲学に革命的な影響を与えた。顕微鏡によって世界を高倍率で捉える と、世界はしだいに断片化し、フラクタル化する。それは、世界に対して、混乱をもたらすのではなくて、「断片の理法」のようなものを与えてくれる。スピノ ザとライプニッツが気づいたのは、世界はどんな微細な部分にいたっても、「理性」に貫かれているという自体であった。スピノザは、人間の感情も思考も、自 然=神という能産的な力の場にあって、その力が自分を表出すべく成長してきたものとしての必然性をもっていると述べた。スピノザにとっては、あらゆるもの (=自然)に、自然=神の理法が宿っているのである(だから、反抗期の息子に、自らの精子を顕微鏡上で見せるならば、彼は、そこに神の理法が働いているの を自ら感知するかもしれない。それこそが、エティカなのである)。
ところで、スピノザによれば、そういったかたちで自然=神の理法に接近 すれば、無秩序で、断片的で、混乱したものなど何もない。力強い、自然=神の理法の哲学が、スピノザによって、打ち立てられたのである。それに対して、ス ピノザにとっては、けがれたもの、邪悪なもの、おぞましいものは、人間が、つくり出した無秩序で、断片的で、混乱した理解の仕方である。そうした、けがれ た不正なものをつくりだす思考や感情を理解するためには、構造人類学の象徴理論を参照するのが手っ取り早い。
ダグラスとリーチが、この問いに挑んだ。ダグラスは、けがれや混沌を外部にあるものとして設定して、内なる秩序が、その外部の曖昧さを取り除こうと努力することによって、かえって、 けがれや混沌を産出すると説いた。リーチは、境界領域をつくり出して、不確実なものに対する不安を減じようとするのだが、そのことがかえって、けがれや混沌を生み出すのだと説いた。ダグラスにせよ、リーチにせよ、けがれや混沌は、思考によって、思考のあとからつくりだされたものでありながら、言語による明 晰な思考の届かない、くすんだ見通しのきかない暗雲のなかに、封じ込められてしまうのである。
それは、上に述べた自然哲学との対比におい て語れば、プラトン~ヘーゲル的な、主=文化による奴=自然への覇権の確立に重なる事態であり、スピノザ=ライプニッツの唱える自然=神の理法が支配する 自然成長する自然観とは真逆の動きを孕む考え方であると見ることができよう。どういうことか。中沢は、言語秩序以前の経験世界は、連続的な生の流れのなか に知覚が乱雑にほうり込まれている混乱したジャングル、経験のアマゾン河であるという。しかし、そのような事態を不安に感じる人は、ジャングルを伐採し て、言語の秩序からなる明晰の小島をつくるという。明晰の小島のなかでは、以前よりも、ジャングルが濃密な、恐ろしいものと感じられるようになる。タブー や儀礼でも引き合いに出さなければ、その繁茂の力を食い止めることができないというのが、これらの構造人類学者の思考の道筋である。
ふた たび、スピノザに戻れば、わたしたちは、そういった、小ぢんまりとした有限の小島において、明晰な秩序づくりにいそしんでいる。ところが、この明晰さこそ が、じつは、無秩序で、断片的で、混乱したものを生み出す源なのである。さらに言えば、わたしたちは、自然との関係において、誰もが、そうした、言語秩序 による明晰の小島の住人となっている。実際には、自然成長する自然だけしかない。そのなかに、人間が対象化する所産的自然(物質的自然)と人間の精神活動 のふたつの表出があるだけである。そのようにして、「自然は飛躍する」(自然成長する)。繁茂し、自然成長する自然を、それとはまったく異質な秩序に組み 入れて「文化化」し、経験レヴェルから切り離された記号―象徴体系を、人間の知性はつくり上げようとする。構造人類学は、そうした自然成長し、繁茂する自 然から、人間の知性を引き離そうとしたのである。
混乱したジャングル、経験のアマゾン河。それは人を不安にする。人間は、ジャングルを伐採し、言語的な秩序によって、ジャングルのなかに明晰の小島をつく る。明晰の小島に住むようになった人間は、ジャングルが以前よりも濃密になり、明晰な思考が届かないものとして、感じられるようになる。ダグラスやリーチといった構造主義者による象徴的思考とは、そうした知性の格好の例である。繁茂するジャングルは、清浄と不浄、秩序と混乱の弁証法的なプロセスによって説 明されるが、そのことによって、けがれや不安は、つねに、濃密なジャングルのなかに封じ込められてしまう。そうした知性のあり方は、スピノザによれば、改 善されなければならない。人間の知性が、自然化して、能産的な自然の純粋な力の場に触れるならば、カオスの闇、混沌、けがれや不安は消失するだろう。
ダ グラスらの構造主義は、人間の知性を、言語によって、自然史から剥離しようとしてきた。言語とは、自然のプロセスからの飛躍によって生み出された、別の言い方をすれば、非連続性に基づいて組み立てられた別の秩序に属するものなのである。ところで、人間の知性を自然史に挿入し、和解させようと企てたのは、レ ヴィ=ストロースであった。しかし、結論から言えば、彼のもくろみは、スピノザの行き方には、たどり着いていない。遠回りして、神話論理の最終巻『裸の 人』に取り上げられたエピソードによりながら、レヴィ=ストロースの論点を追ってみよう。
16ミリカメラを手渡されたナバホの人たちは、 映像を記録する過程で、機織の前に座った婦人がナバホ織を織り上げるというプロセスに興味関心を示さず、糸を運搬していく光景ばかりを丹念に記録したりし た。それは、パラディグマ軸の方向に映像をつむぎ出すのではなく、シンタグム軸の方向に、分解実験を行おうとしたということになる。彼らは、(わたしたち の)ハリウッド映画のように、言語秩序によって補強しながら、「上向的」プロセスをつうじて、物語を織り上げていくのではなくて、それとは反対向きに、 「下向的」プロセスをつうじて、構造化のプロセスを分解しようとしたのである。レヴィ=ストロースは、前者を、自然史のプロセスから切り離された言語、構 造を組み合わせて、つまり、非連続化することによって、「上向的」に神話を生み出そうとする情熱に、後者を、わずらわしいほどの細目に覆われ、反復をくり かえし、わざと極度に手の込んだ遊びに興じているかのように、つまり、生の流れの連続性を取り戻すがように、「下向的」に儀礼にいそしむ態度に対応させて いる。ナバホたちは、神話に向かう傾向が取りこぼしてしまう連続的な生の流れを回復しようとする欲望を実現する道具として、映像テクノロジーを捉えたのだ と、レヴィ=ストロースはいう。
シンタグムの分解は、メトニミーに対応しており、微分化するという点で、儀礼に重なる(他方、パラディグ マの拡大は、メタファーに、積分化に、神話に、重なる)。レヴィ=ストロースによれば、「儀礼を行う人は、動物に混じり、彼らの同類になり、性的な放縦や 親族関係の混乱がしめす『自然状態』を、ふたたび生きることになる」という。しかし、儀礼とは、生の流れの連続性を回復しようとする望みにかけるが、けっ して、思考の外部に出ることはないという意味で、思考のデカダンスであり、儀礼によるかぎり、人間は、自然史のなかに統合される望みを初めから絶たれてい ると、レヴィ=ストロースはいう。しかしながら、奇妙なことに、彼にとって、非連続の原理(神話、「上向的」プロセス、パラディグマ)こそが、人間を自然 史のなかに統合しようとする構造主義の希望であると述べる。
レヴィ=ストロースのいう「自然」とは、結局のところ、美しいタンポポの花の ように、思考のプロセスに内在するものと同じ非連続性の原理にしたがって、畸形化、怪物化することのない、「目的論的知性」を内蔵した自然のことだということになる。しかし、非連続性を実現している形態など、自然のなかに存在するのだろうか。そうしたレヴィ=ストロースの「上向的」な、神話へと向かう情熱 を、自然と重ね合わせることなどできるのだろうか。徹底的に、「下向的」になり、生の流れの連続性を取り戻すような欲望へと降りてゆかなければならないの ではないか。
中沢による、レヴィ=ストロースの乗り越えはこうだ。「レヴィ=ストロースは神話的思考のなかに、『目的論的理性』のもっとも純粋な結晶状態を見て、その結晶をとおして大脳の『自然』を外の世界の『自然』のうちに包み込み、統合しようとした。だが、このような状態のうちに『人 間を自然のうちに統合』できると考えるのは、幻想にすぎない。思考のほうが『目的論的理性』の限界を超えて、『無限化』をめざしていかなければならないの だ。そのとき思考の生成をつき動かしている純粋な力は、文字どおり『自然な成長状態』を実現する。知性を『自然化』し『森林化』して『無限化』することが できたときにはじめて、『改善』された知性は晴れ晴れとした自由のなかで、自然と精神をともに貫いて、そのそれぞれを無限の多様体として作りなしていく純 粋な力の場に触れていくことができるのだ」。
第5回研究会(2009年4月3日)

ロマーン・ヤコブソン「言語の二つの面と失語症の二つのタイプ」『一般言語学』
わたしたちは、言語学の立 場から、失語症を解明しようとしたヤコブソンの先駆的な試み(ローマン・ヤコブソン「言語の二つの面と失語症の二つのタイプ」)に寄り添いながら、最初 に、言語の持つ二つの面について検討し、つづいて、言語とパラレルに構造化されている「無意識」の意味について議論した。その結果として、ヤコブソンの構 造言語学が、いったい、どのように、レヴィ=ストロースの構造主義へと流れ込んでいったのか、さらには、そうした構造主義のアイデアを介して、わたしたち は、ヒトの心の働きを、どのように捉えればいいのかについて、ある見方を抉出することになった。
最初に確認したのは、言語の二つの側面に ついてである。シンタグマは、語をどのように並べるかという統辞であり、パラディグマは、語を置き換える範列である。別の言い方をすれば、シンタグマは、 言葉の結合であり、パラディグマは、言葉の選択に関わっている。さらには、言語のシンタグマの軸には、部分が全体を現すメトニミー(換喩)が、パラディグ マ軸には、類似に基づくメタファー(隠喩)が対応している。
ヤコブソンによれば、失語症には二つのタイプがあり、そのそれぞれは、「結 合」能力(シンタグマ軸)の欠如と「選択」能力(パラディグマ軸)の欠如に照応する。一方で、結合能力の異常とは、シンタグマ的な、すなわち、メトニミー 的な、「隣接性」の異常であり、逆に、「相似性」が優越するような状況を指す。そういった「隣接性」の異常による失語症は、語の統辞を失う。例えば、 「えっと、学校・・・休んださっき・・・」というような、語の統辞に欠ける発話を行うことになる。
他方で、選択能力の異常とは、パラディ グマ的な、すなわち、メタファー的な、「相似性」の異常であり、逆に、「隣接性」が優越するような状況を指す。そういった「相似性」の異常による失語症 は、語そのものを失う。目の前にあるモノについて言うことができない。しかし、それを、文脈のなかで適切に用いることはできる。発話としては、例えば、 「えっと、あれは、どうなりましたかね、それもそうだけど・・・」というようなものであろう。
しかし、こういったまとめ方は、事柄を、あ まりにも単純化しすぎるものになっているのかもしれない。事実は、言語の複雑さと連動して、もっともっと複雑である。音素のレベルで、結合と選択に異常を きたす場合もある(例:pig →fig)。いやむしろ、実際には、そうした言語学研究の過程で、上のようなヤコブソンの研究へとたどり着いたのではないだろうか。
興味 深いのは、「弁別特性」についてである。ある言語には、その言語の範囲内で見出される「弁別特性」がある。あらゆる音素は、母音性や子音性、高音調性、低 音調性などの指標によって、+-の価値によって表すことができる(ある音素が、母音と子音の両方の弁別特性をもつ言語があるともいう)。ヤコブソンの「弁 別特性」をめぐる業績は、わたしたちの話している言葉が、デジタル信号のように構造化されていることを顕著に示している。つまり、驚くべきことに、そし て、レヴィ=ストロースが見出したように、わたしたちの内的自然は、「目的論的理性」とでもいうべきものに支配されているのである。
話がそれたが、本筋へと戻れば、わたしたちは、(失語症の苦しさを知らないがためにこういった表現にならざるを得ないが)ある意味で、誰もが、潜在的に失語症なのである。時に応じて、ヒトは、言葉を失う。
と ころで、ヒトは、どういったときに、言葉を失うのだろうか?フロイトが、そのことを考えてみるための手がかりとなる。夢の構造を突き止めるなかで、フロイ トは、象徴や時間系列が、語を転置する、シンタグマ的な「置き換え」と、意味を圧縮するような、パラディグマ的な「圧縮」とによって構成されることを指摘 した(のだと、ヤコブソンを微調整して、整理しておくことにしよう)。
そういった置き換えと圧縮が、夢を見ているような「無意識」の状況 において起こるのだとすれば、わたしたちは、中沢新一の以下の言葉に同意することになる。「流動的知性である無意識のしめす特徴的な運動が、意識の働きを 生み出す言語の構造と、とてもよく似たところを持っている」(対称性人類学)。わたしたちの喋っている言語は、「無意識」のレベルで、それとほぼ構造的に パラレルなものを、潜在的に持っていることになる。
ひるがえって述べれば、そうした「無意識」とは、言葉によって抑圧されたものではなく て、レヴィ=ストロース的な意味での、それ自体が、独自の理性であるところの「目的論的理性」であるということになる。だとすれば、そうした「無意識」 を、わたしたちは、それこそがヒトの知性であると信じて疑わない言語の秩序によって抑圧されてしまった状態から、引き上げてやらなければならない。二次的 過程として「すでに構成された秩序」の側から、ストーリーがむちゃくちゃな夢や言い間違いとして、無意識の側から突き上げてくる「みずからを構成しつつあ る秩序」として、抑圧したまま理解するのではない、別の手続きを見出さなければならない。そうした「無意識」(とりあえず、ここでは、この言葉を使ってお く)を持つことによって、ヒトの心は、現実世界から自由であることが可能となったという事実に対して、より高い価値を置くべきなのである。
レ ヴィ=ストロースの構造論を経由して、「無意識」をめぐる新しい思考のステージへとたどり着いた。そのとき、わたしたちは、「レヴィ=ストロースの方法は たんに分析の技術にとどまるものではなく、人間文化の深層にある一連の変形規則群を明るみにだすことによって、西欧中心の近代思考体系への根底的反省をう ながす力を秘めていることになる・・・自らブリコラージュを演ずる精神のもち主でなければ、構造主義的分析のこころみは野生の思考とは異質な図式をいたず らに生みおとすおそれがある」(関一敏)という洞察に、深くうなずくことになる。
第6回研究会(2009年4月22日)
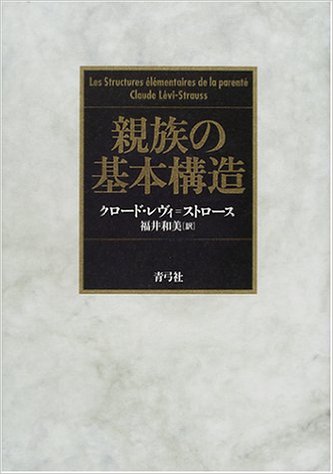
レヴィ=ストロースの「自然と文化」『親族の基本構造』
1949年に書かれたレヴィ=ストロースの「自然と文化」は、いまもって、自然と文化、自 然状態と社会的状態を考える上で、きわめて示唆に富んでいる。先史学や霊長類学のその後の発展が、論述内容の緻密さを格段に高めているにもかかわらず、レ ヴィ=ストロースの思考は、いささかも揺らぐようなことないように見える。自然とは、人間のもとにある普遍的なものであり、他方で、文化とは、規範に拘束 されるものであるという言い回しには、古びた感じがまったくしないどころか、新しい感じさえする。
最初は、社会組織をまったく欠いてい た人類が、その後、文化の形成に不可欠なさまざまな活動の形態を発達させるようになった。その意味で、自然状態から社会状態への移行という人類進化の一局 面は、難題である。言語活動、石器加工、埋葬儀礼などを行っていたネアンデルタール人たちは、自然状態で生活していたとは考えられないが、後続する新石器 時代の人類からは、絶対的に分かたれる。人間は、一個の生物であり、同時に、一個の社会的個体なのである。
外的・内的刺激に対する人間 の応答には、人間の本性(瞳孔反射など)に由来するものもあれば、人間が置かれる状況(手綱に触れるや即座に定まる旗手の手の位置)に由来するものもあ る。いったい、どこで自然は終わり、どこで文化は始まるのであろうか?隔離状態における新生児の応答は、心理―生物的起源に根ざし、後発の文化的総合には 由来しないと仮定できるが、隔離状況はそもそも文化的環境に劣らず人為的である。また、数々のデータから類推すれば、「野生児」「オオカミ少年」「ヒヒ少 年」もまた、文化的な怪物であって、どう転んでも文化以前の状態の忠実な証人ではない。要は、人間のなかに、文化以前的性格を帯びた行動類型の例証を見出 すことはできないのである。つまり、自然と文化の境界を、どこかにはっきりと定めることは不可能なのである。
それでは、動物の生活の高 度な水準から出発して、文化の輪郭、文化の前兆と認めうる態度や現象をつかむことは可能であろうか?類人猿には、単語を分節できるようになるものもあり、 ある程度までなら道具を使いこなすことができるが、それらの兆候はすべてもっとも原初的な現われの域を出ず、しかも根本的な不可能性であるかのように見え る。つまり、巧みな観察を無数に重ねることで埋められるかもしれないと思われてきた溝は、逆に、一段と飛び越えがたいものとして現れてくるのである。
しかし、それよりも格段に重要なことは、サルたちの社会生活には、明確な規範を形成する準備がまったく整っていないということである。大型ザルでは、哺乳 類に見られる本能的なふるまいが弱まっているが、代わりに新しい平面でなんらかの規範をつくるところまではいけない。本能(=自然)が弱まる一方で、自然 が去ったあとの領域は更地のまま残されている。
じつは、こうした行動における規則のなさが、自然過程を文化過程から区別してくれるもっ とも確実な基準となる。いいかえれば、制度的規則について、その起源を自然のなかに求めようとすることに、そもそも推論の誤りがあるのだ。要するに、自然 と文化が連続しているとの誤った見かけに、二つの次元の対立地点を明らかにするように求めることはできないのである。そういったことから何が言えるのかと いうと、その場に規則が現れるなら、例外なく文化段階にいることになり、他方で、自然の判別基準は普遍的なもののなかに認められることになる。
人間に共通する恒常的なものは、習俗、技術、制度など、人間集団の相違と対立を形づくるものの領域外にある。それゆえに、以下のように仮定することができ る。人間のもとにある普遍的なものはなんであれ自然の次元にあり、自然発生を特徴とする。他方で、規範に拘束されるものは文化に属し、相対的・個別的なも のの属性を示す。そのうち、インセスト禁忌は、規範および普遍性を、いささかの曖昧さもなく、しかも不即不離のかたちで示す。インセスト禁忌が、なぜ規則 であって普遍性という性格をもつのかというと、いかなる婚姻型も禁忌とされない集団があるかというと、そんなものは絶対にありはしないからである。した がって、それは、自然的事象のもつ特徴的性格と文化事象のもつ特徴的性格を同時に示すのである。
文化人類学のページへ