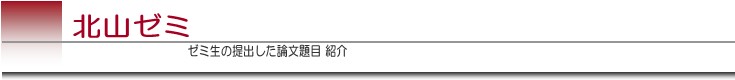
2006
◆差別を取り巻く社会的力線の分析と差別者の構成〜インターネット匿名掲示板の部落差別発言を対象として
2009
◆消費社会の中の「男性身体」 〜交錯する「男らしさ」と「マスキュリニティ」の行方
1999
◆子供部屋 〜家族・住居・子ども・子供部屋の歴史的変遷
◆循環と消滅 −文化ネットワークのモデリング−
◆美術館の歴史と現代社会における在り方
◆体臭の無臭化
◆劇場空間の公共性と舞台芸術文化の政策的支援における再検討
◆本質的なるものを超えるための試論 −琉球弧から「本土」への移動とその「本土」での生活・文化研究の視点から−
◆南太平洋島嶼諸国のマグロ産業 −経済的自立にむけて
2000
◆日本における海外文化受容 〜絵画の視点から
◆日本における「中央」−「地方」の関係性について
◆比較文明学的なマーケティングに関する試論 −地域の文化施設の活性化を目指して−
◆「イメージのいれずみ −装いの新時代へ−」
2001
◆「テレビゲームの理論系」
◆『芸術・文化支援の社会的システムにおけるパラダイム転換』
◆エチケットにみられる近代生活様式の文明化
◆80年代の『オリーブ』を中心とする少女雑誌論
◆芸術と生きるシカケ −美術館、その周辺機関の機能および可能性に関するアートマネージメント的検討−
◆新しい連帯のかたちへ "Le pacte civil de solidarité
2002
◆男性(おとこ)服と日本社会〜1980年代から現代までのスーツを中心とした男性の装いに関するー考察〜
◆生殖医療の文化的背景の考察−看護師へのインタビュー調査を中心に−
◆生きることへの欲望および思考のあり方に関する可能性について
◆「私探し」と「キャラクター文化」
◆「ナシ族/トンバ文化」の構成と循環−聖地の構成と変遷
◆「戦後民主主義」とは何だったのか
◆イメージになる身体、開かれる皮膚
2003
◆衣によるエスニック・アイデンティティの表現とジェンダー −「チマ・チョゴリ制服」誕生と女性たちのエイジェンシー―
◆実践と論考に抽象的思考と観念的思考の循環をみる―シナリオ・映像制作における思考の過程をめぐって―
◆芸術文化の振興と評価―意義を問われる美術館
◆「学校施設と身体〜いすを中心に」
◆セクシュアル・ハラスメント概念への考察
◆「聴覚人間の編成―コルシカ島(フランス)の音楽文化の衰退と復興を事例に―
◆筆記具、筆記行為の変遷と「書く」の今後に関する分析
◆音楽家ピエール・ブーレーズに見る「脱解釈」という試み
◆ボディイメージとその質感について 視覚化する「わたし」の変容
2004
◆口紅と口紅広告からみた戦後女性史―1960年代を中心に―
◆オタク〜その虚像と実像
◆「環境広告」の実態 〜日本経済新聞(1990年から2003年各年度)1月1日掲載分から〜
◆都市伝説と都市の変貌 〜創造する都市の行方〜
2005
◆日本の<エスニック>料理
◆『「下北沢」の終焉』 〜「下北沢」の誕生から終焉まで、都市計画の問題点と1980年代の消費分析を手がかりに、衰退する町の現状分析と変遷に関する考察〜
◆日本における現代美術の現状と考察 現代美術家村上隆の戦略性と諸活動を軸に
◆「スーツ」を着る身体 -近代理性とアンチ近代理性の対峙の場として-
2006
◆江戸商人の衣類表象 ―階層化された構造と色のシンボル―
◆1960年代のブライダル産業
◆消費社会とデザイン概念 ―田中一光からみる戦後日本のデザイン論―
◆ゲイのエイジング研究 ―老いのロールモデルを求めて
2007
◆路上の<私>のつくり方〜雑誌「FRUiTS」にみる、文節化する衣服=身体とその背景に関する一考察〜
◆まちづくりの考察ー外の人間のまちづくりについて
◆絵画のヒステリー、平面上のサハラ ジル・ドゥルーズ『感覚の論理』における身体について
◆「現代のきものブームにおけるインターネットの関わりについて」
◆一九八〇年代までの素顔と自然に見える化粧
2008
◆メイド喫茶の転遷とオタク文化の一般化に関する考察
◆『宇宙を形創るとはなにか―江戸時代と天文学』
◆食の安全性から見た現代の健康食ブームの課題と問題点
◆「国境との距離」―<周縁>小笠原から見えてくるもの―
◆「アートの『外部』としての『アート・マネジメント』 ―日本のアート・マネジメントに見る問題と『ランド・アート』『モエレ沼公園』という事例」―
2009
◆パフォーマンスとしてみたセックスワーカー・アクティヴィティ −アジア太平洋地域を事例に−
◆オウム真理教と村上春樹 −信者はなぜ入信し、そこに留まり続けるのか−
◆絶景、三百メートルの《ボレロ》
◆マンガを原作とするミュージカルの行く先 −"漫画×舞台"が生みだすもの−
2009
2003
◆現場の声を生かす新しい青年海外協力隊として
◆自律型社会を支える住民参加型まちづくりと公共的位置付けに関する研究
◆検証 民意を反映させる行政の仕組み 〜市民陪審制度の構築〜
◆文化政策論と地方自治体の文化政策−地方自治体文化政策を支援する文化政策論の形成をめざして−
◆公共図書館の可能性 情報提供・コミュニティ
◆産業・組織における職業性ストレスへの対応に関する研究 〜キャリア開発の視点からみたキャリア中期の危機のストレスとその対策の検討
◆共創化社会の構想 コミュニティ・マネジメントの基本スタンス
2004
◆企業の社会貢献活動における積極的活動要因の考察
◆1970年代から80年代にかけて地方自治体の文化行政の描いた文化像
◆現代社会におけるボディ・イメージに関する考察 スリム志向化と消費の視点から
◆市民の情報リテラシー支援における公共図書館の社会的役割に関する研究〜市民を対象とした講座の事例研究を通じて〜
◆芸術文化事業のための文化経営技法
◆支援の思想、支援者の生き方ー水俣の事例からー
◆「母性による子育てから感性による子育てへの転換」〜NPO彩の子ネットの活動を通して父親・専門家参加型ネットワークによる母性解体から多彩なライフスタイルを目指す〜
◆大都市近郊地域(住工混在地域)における中小企業ネットワーク形成のための要因分析〜調布市の場合を中心として〜
2005
◆総合型地域スポーツクラブの設立状況と社会的役割〜山梨県における形成事例〜
◆若年就労問題に関する一考察〜「ニート」論に見る問題解決への端緒
◆ミュージアム・サービス論〜ミュージアム・サービスと利用者との関係性についての一考察〜
◆身体をみつめるワークショップ」の可能性と課題〜現代の演劇ワークショップ事例研究を中心に〜
◆新しい公共性とアドボカシー ―法と正義の視点から―
◆東京都交響楽団のマネジメントにおける一考察〜自治体の芸術文化組織として〜
2006
◆消費社会における出産―出産体験者への調査を事例として―
◆日本におけるゲイ・バイセクシュアル男性の現状とサポート・リソースに関する考察
◆NGO/NPOにおけるクリエイティブコミュニケーションの重要性に関する研究
◆わが国の中途身体障害者の自立と社会参加について―当事者の視点から見た障害者福祉の現状と提言―
◆自助と共助のグループ研究―子育て支援市民活動の継続性の考察―
◆吃音者の「社会」を巡って〜治療と受容を超えて〜
◆知的な障害のある人々にコンピュータ利用は何をもたらすか〜知的障害者厚生施設利用者のコンピュータトライアルを通して〜
◆『CSRは日本の個人主義にどのような影響をもたらすのか〜企業アイデンティティをめぐるトレンドへの期待について〜
◆ 『博物館ボランティアによる教育普及活動の実践』―博物館を「学びと新たな発見の場」にするために―
◆テレビジャーナリズムの確立に向けて―現場教育と大学教育の融合と協同連携の一考察―
◆特別な教育的ニーズを持った子どもたちへの教育に関する英国との比較と考察
2007
◆市民音楽祭は「サステナブル都市」の主要対策となりうるか?
◆個人の「日常」と環境、そして社会の情報フロー、その相互作用の調査−知恵を媒介するものへ−
◆研究開発型NPOの可能性に関する考察−日本の事例をもとに−
◆化粧の心体的効用に関する考察−高齢社会におけるQOL向上と化粧の調査−
◆正当性をめぐる思想の中に予言を見るルワンダ紛争、その定性分析と定量化の試み人間の英知である思想と、定性的そして定量的分析は紛争を予見する、という仮説
◆日本におけるチャイルド・ライフ・スペシャリスト(CLS・CCLS)導入促進に関する研究
2008
◆ユーゴ紛争における非民族要素の一考察―クロアチアのケース・スタディー―
◆市民参加社会における町内会機能論―その存在意義と常設事務局の設置によるプラットフォーム化―
◆「21世紀に期待される公共性の方向」―GRIガイドライン適用状況調査を踏まえて―
◆不利な立場におかれた若者たちの実相―フリーター・若年無業者の就労問題を中心に―
◆消費されるアイデンティティをめぐる考察 ディスプレイ化する社会
◆「日本におけるスクールソーシャルワークの可能性とその効果」
◆変容する社会とCSR 社会貢献活動の新たな価値について
2009
◆豆本と豆本より派生する諸相への一考察
◆「雇用管理とキャリア形成に関する課題研究」〜若年者の非正規社員を中心に〜
◆ドイツの成人教育〜社会的包摂策の視点からみるその役割と今後の課題〜
◆在日系ブラジル人のアイデンティティに関する考察
◆「アイデンティティ」とは何か―他者論・親密論との関係とその応用―
◆ワーク・ライフ・バランスに関連する法制度の比較−日本でワーク・ライフ・バランスを浸透させるために−
◆『同盟グラフ』1940-1945におけるインド報道〜一元的情報で語られた、大東亜共栄圏外の人たち〜
◆社会貢献型消費の課題と展望―社会貢献の選択肢を広げる消費の可能性―
◆定点観測は時代の指向性・思考性を示す、という仮説<ストリートファッションマーケティング>分析の方法と有効性について
◆日本人の「言挙げしない精神」とは何か
======================Back
to Top...