<主催者であるESD研究センター・センター長阿部治からの挨拶概要>
こんばんは。本日のシンポジウムは、立教学院の135周年記念事業の一環として、持続可能な社会に向けて、大学が果たす役割について考えることである。例えば、大学で学んだことを社会に出て生かすためのカリキュラムなど。また、持続可能な社会に向けて、楽しく行うことも大事。このような大学のネットワークを、HESD(Higher Education For Sustainable Development)ともいう。
今回のような、大学がエコグッズを作ることは、大学側の収入にもなるだけでなく、エコグッズをつくるプロセスをもって、持続可能な社会にどう関わるかが、この企画の趣旨である。そして、これらは、立教だけでできるものではない。本日は、明治・上智の大森先生、鬼頭先生をお招きしている。
エコグッズはいろいろある。例えば、立教大学の“かっとばし”。これは、立教の中でも評判がよく、2200本ぐらい販売されている。
今回、コンテストを開催するが、環境グッズ・エコグッズのイメージは簡単にはわかないものである。そこで、「一秒の世界」で有名なThink the Earthをお招きし、アイデアのきっかけ、あるいはどのように出てくるか、を話していただく。また、中西氏はアイデア勝負の広告会社に勤めており、ワークショップが得意な方である。本日は、ワークショップを実際にやってもらう予定であり、アイデアを落としてもらう。
大学での取り組みとアイデア作りを、楽しく、行うことが、本日の集まりの意図である。
第1部 各大学での取り組み
1.立教大学-阿部治
大学として、SDにどう貢献・責任があるか。環境教育・ESDとしての課題とは何か。持続可能性に向けて、地球温暖化など複雑な関係であり、一つの問題を解決すればできるものでもないし、個別の研究者だけで、解決できるものでもない。
①持続可能性をベースとした学問の再構成
総合科学の再考や、サステナビリティ学など地球的課題を扱った新たな学問分野など、従来の教育活動だけではなく、再構成を行う。
②持続可能な社会への変革を教育・研究・社会連携
受動的な学生ではなく、問題に直面したら解決できる学生を育てる。例えば、アクションリサーチなどを取り入れる。行動変容を促す、そのための研究、学問、社会経験などが考えられる。また、MDGs(ミレニアムゴール)の途上国の問題など、2015年までにクリアする。グローバルコンテキストを考える。
③ローカルコンテキストを意識した教育・研究・社会連携
ローカルコンテストを意識した教育。持続可能な地域づくりに大学が関与していく。
④環境教育指導者の養成
指導者の養成。CR(cooperate)CSRは企業だけではなく、大学の責任もある。社会的に責任があり、本来、大学のミッションとして出さなければならない。カリキュラム、SDのキャンパスなど。
持続可能な社会に果たす大学の役割として、研究・教育・経営・連携が必要。
①研究
・教員の個別研究
・ESD研究センター
②カリキュラム
・全カリおよび学部・大学院(環境系、サステナビリティなど。組織的にはまだ)
③経営
・経営(グリーンキャンパス)、ビオトープ(バタフライガーデン)の創造、環境マネージメントシステム 環境マネジメントシステムが確立していない。大学に要求している。今、確立していない大学のほう
が少ない。
④連携(地域、全国、国際)
・豊島区・池袋西口商店街、ジャコウアゲハプロジェクト、ESD研究センター・エコオペラ、KEEP協会
、高畠町、陸前高田市、HESD、環境人材育成コンソーシアム、Prosper-Net、ツバル青少年友の
会。
豊島区内、ヒートアイランド現象がおきている。また、構内に珍しいジャコウアゲハがいる。キープ協
会は清里にある、日本の環境教育のメッカ。立教が中心となって、ツバルから二人の高校生を日本
に呼び、高校に入学しているなど。
2.上智大学-鬼頭宏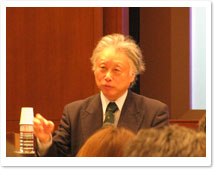
もくろみは立教大学と一緒である。
上智大学は立教とは宗派が違う。立教よりも、若くて96歳、4年たつと100周年になる。
大学の教育理念は男も女も他の人のために。世の中に入って、他の人のために。よって、途上国や災害の活動など、活発である。
21世紀になって、持続可能性は人類にとっての課題である。21世紀は一つの転換でもある。
1960年代のボンデックのケース・ボールディングを参考に。
一つ目は、人口爆発は、年率30%の国もある。最近、少し落ち着いてきた。
二つ目は、経済的離陸、エコノミックテイクオフ。低開発の状態から出る。しかし、下が発達しないと上も発達しない。
三つ目は、戦争。ベトナムで大々的に展開され、東西冷戦の時代。オバマは話しただけでノーベル賞をもらった。核戦争の危機。
四つ目はエントロピーの危機。熱力学、エネルギー、資源、あるいは社会の活性の危機。エネルギー資源の枯渇を指摘。
本が出たのは60年代だが、その直後、70年代に石油危機、資源枯渇が身近に感じられるようになった。本当に起こるんだと、身近なものになった。それから45年。最近になると、人口問題はなんとか収まり、経済的離陸、ブリックスもなんとか解決している。しかし、環境や資源のことはまだである。昔は汚染源が、化学工場などはっきりしていたが、今は目に見えない。そして、汚染ではなく、破壊もしている。人間の生活舞台そのものが危機に陥っている。
ユネスコが中心となってESDを行っている。他の人のために何ができるか。環境問題は重要である。
大学の中に環境リテラシーを見つけて欲しい。21世紀を生きる人にとって、環境に配慮しないで暮らすことはできない。知ることだけでなく、身をもって行動できる人が必要である。
環境法学科、大学院、地球環境など、そこで専門的に学ぶだけでなく、環境のことを一生懸命になって考え、行動していく人が必要である。
全学共通カリキュラムの中に、環境の授業を増やし、これまで23科目(直接環境に関わるもの)、2000人ぐらいが履修している。これは、平均して一科目とっていることになる。これをつなげて高度にしていくことが必要である。
大学のCRとしては、経営として、推進委員会を作った。しかし、制度を作っても、会議を開いていないのが実情である。特に、今はインフルエンザ対策などに追われている。
今年から、アジア大学間ネットワーク、環境人材育成として、例えば、金融、地域研究も含めた幅広い環境教育を進めている。
いろいろあるが、環境会議、サークルなど、学生自身がやってくれている。
今後、立教大学、近くの明治や法政などと、連携してやっていきたい。
3.明治大学-大森正之
環境経済学を担当している。
先週、ノーベル経済学賞に、女性が選ばれた。その女性の、専門が環境経済学というのが画期的である。
エコ・テクノストラクチャー=環境省の環境人材に取り組んでいる。
大学は地域にあるので、地域と行っていく。
全学というわけではないが、各学部で新しい科目を新設している。そのため、環境コミュニケーション、マーケティングなど、教員をあわてて公募した。
理科系の学部の学生も単位が取得できるように、学部間共通総合講座を持っている。これは、専門科目の基礎になるような授業である。現在のカリキュラムは、議員とか、企業のCSRの担当者を招くなど、現場の声を聞いている。
地域社会との関係となると、3つキャンバスがあり、市民の公開講座を行ってきた。2000年以降は、やっていない。ISO14001を、地域経営体としての取り組みとして推進するとき、委員の一人として、なぜお金を払って、環境コンサルに任すのかが疑問である。早稲田のように、教職員・学生の参加をなぜさせないのか。競争の材料にされているのが現状である。また、教職員に対してかなりの作業になる。取得そして、更新をしなければならないからだ。ただし、このプロセスの中でよかったのは、学生が少し参加して、内部監査の資格を取ることがあったことである。また、若干の効果ではあるが、ごみはかなり減っている。ただ、新しい施設を作ったり、ただコピなど、も行われている。また、電気の使用量は減っている。例えば、トイレなどは入らなければ消えるなど。多大な労力とコストにも関わらず、認識は深まったというのは確かである。しかし、地域社会との連携はやってはいるがあくまで個人プレーで、大学のミッションとしているわけではない。今後の課題は、大学として明確なミッションとして、様々な教員がいるばらばらな状況の中で、お互いの専門・学問の壁を取り払って、コミュニケーションを図ることが必要である。
2010年、水俣・明治大学展を開催することになった。水俣の資料展示など、公害の原点でもある。明治の付属校を呼んだりもする。リアルな場を作っていきたい。
学部間共通総合講座は100人ぐらいしかない。宣伝不足かもしれない。なぜ学生がのめりこんでくれないのか?ESDを主体的に受けてくれた学生が、就職したり、何か活動していても、最終決定部署に就職できないという、ジョブがある。ぜひ立教大学の学生にもきてもらいたい。数少ない、意欲のある学生しか授業を受けられず、もったいないのでぜひ受けてもらいたい。
シンポジニストとのディスカッション
阿部:大学でやっていくのは難しいと実感した。エコアクションなど。一人の教員だけではできないが、ミッションのある教員が行っていく。
鬼頭:三菱商事から寄付をいただき、講座を開いた。200人ぐらいが参加した。
大森:12月のエコプロダクツなど、急速に最近参加者が増えている。同僚の経営、社会学の教員は、学生が参加して教員に質問してほしいと、積極的に言っている。
阿部:上智の学生は熱心である。立教では、学生と西口の環境をよくしようと活動している。文化祭のごみ分別など。これは、大学の実行委員会に今年から移転した。また、環境就職セミナーは年2回ほど、企業のCSR担当者をお呼びして行っている。今度は、パナソニックとNHKを呼部予定である。多い学生のなかで参加者100人ぐらいと少ないが、このような活動が、ルーティンとなり、継続していくかにある。学生にとって、いろんな取り組みがあるので、新しいものになるべくどんどん参加して欲しい。また、外にも学生サークルなどあるので、出て欲しいし、そのような外のアイデアを中にも入れてきて欲しい。4年で卒業してしまうが、企業というのは学生があってのもの。教員からではなく、学生同士で、自分たちが主役だと思って、大学を変える意見を言ってほしい。
鬼頭:上智には森があり、大学を卒業してからも大学とつながっていけるような仕組みを作っている。
阿部:セカンドステージも人気で、卒業生やOBなどが参加している。
第2部 企業・NPOの取り組みと、エコグッズのためのアイデア作り
1.Think the Earth-山口倫之
初めてはいったのですが、立教大学はきれい。
NPOでもあるがスペースポートとして企業で企画・製作をしている。NPOでもあり、企業でもあることはあるいみ強みでもある。
いろいろな活動があるが、大事なことが4つある。伝えることをメインに、コミュニケーションを図ることである。エコグッズとは何か?といわれると、3Rに沿ったものが多い。
まず、素材がエコロジーのもの。杉の木がたくさんあって、間伐材でほっとかれたものを使用するなど。シートベルト、エアバックの素材など丈夫なものから作ったりする。
次に、機能的にも優れたもの。四万十ヒノキの入浴、ポプリなど。
インドネシアのラジオは、地元の木材を使って、地元の人が使えて、デザインのあるものなど。この制作方法は、ピープルツリーのフェアトレードやマザーハウスなど情熱大陸や若い女性に人気がある。バングラのものは、先進国でも売れるデザインにしてある。地産地消、地元のものを使う。
織物が自然エネルギーで作られているもの(愛媛県)。
使うこと自体がエコ、SIGGボトルなど、リデュースの効果。頑固本舗は、自然界に残らず、一週間で99%分解する。
使うことで関心を引き起こすもので、ビジュアル・エコ・ブックシリーズ。
見せ掛けで、デザイン力によるもの。auの携帯で、Live eaerth、身近に地球を感じる。また、月の使用料を、寄付金としているので、社会に参加していることにもなる。地球を身近に感じて、商品を考えている。例えば、1日何回地球のことを思うだろう。無関心やあきらめの心を減らして、地球のことを考える人を増やす。感性を養う。メッセージを投げるだけでなく、受けたことによってもどうなるかも考えている。
地球時間が分かる(時計)。宇宙からの視点を全ての人に見てもらいたい。いつでも地球を感じられるように。見方が特殊で、24時間で一回りする。
ビジュアルブックは、山の手のテレビで放映していた。TBSが原作。例えば、1秒間にコーヒー1万9000杯、5分で550万杯消費している。身近な問題を掘り起こして考えるための本である。遠くの問題を身近に考える。
21世紀は水の世紀といわれている。石油から水の争奪とも言われている。SIGG社のマイボトルを促進するために、デザインを作成した。給水ポイントのイベントなど。
他に、カレンダー、暦なども作成。
雷バックは、ゼロから企画し、中間NPOとしての立場として製作した。知的障害者の福祉作業所が製作し、米袋をカッティングしてデザインした。
作り手たちの様子(写真)。当初、企画(サイズなど)がばらばらだったが、その後一律化して(直した)。材料は、ただでもらった。例えば、地元の弁当屋さんなど。米袋は3重で丈夫。最後は、アイロンでくっつける。毎回、デザインがかわってくる。
販売先となると、NPOが苦手な分野である。いろんな人に伝えたいということで、国内の販売、国立新美術館、展示会など。物じゃないものも売るなど、ユニークである。海外では、スーベニア東京にバイアーが来てた時に、目をつけてもらい、NYのモマショップで販売している。また、フランの展示会など。
物を使ってもらうことで、地球を考えてもらうプロダクツメイクを考えている。
 フロアーからの質問 フロアーからの質問
フロアー:ライブアース以外は、電気を使わず、風力など、電気使用を使わないように考えることを提案したい。
山口:例えば、ソーラーパネルなどは考えている。
阿部:大学とコラボとするとしたらどうか。
山口:大学は、人がリソース。例えば、立教なら池袋という、地域や立地、立教大学の個性など、例えば、かっとばしなど強みを発掘しながら考えていく。
2.立教大学-中西紹一
135周年記念事業のロゴのコンセプトを作ったプロジェクトチームの一人である。
どういう発想をするとプロダクトができるのかを考えてみる。学生なので、大胆に考えてもらいたい。発想の共通点はよく観察し、置き換えるということ。例えば、ブルーミンという商品。この商品はなんだと思うか。ライト?空気清浄機?芳香剤?実は、加湿器。結局製品化できなかったが。ニイハウスのアーティストが考えた。加湿器で面倒くさいことは?掃除?実は、水の入れ替え。タンクを引き出してなど。花に水遣りは面倒ではない、ということで、花の形にした。
これは、加湿器のデザインをしているのではない。人が水をやってストレスを感じない、作法をデザインした。物をデザインしているわけではなく、人のライフスタイルを考えた。
周りを観察することが大事。物を作る、デザインを作るという事は、ものすごい観察力がいる。そして、新しいものに置き換える。商品を作るときに非常に重要。エコグッズを考えるときに、すごいものを考えるのではなく、人のスタイルをどう変えるかを観察することから始めてみる。一番身近な商品、例えば箸など。これは人の作法を変えている。
布バックは床に置くと、汚くなるので、金具を4つつけたりする。では、汚く見えないためにはどうすればいいのか?床において汚くないもの。それは、靴。つまり、底に上履きがある上履きバック。これも、観察して置き換えたもの。
アーティストとは極端な人、頭が飛んでる人。ポストペットを作った人で、運転があまりうまくなかった。高速の合流で入れてくれた時に「ありがとう」を伝える場合にどうするか?後ろに文字をつける?ランプに顔をつける。「ありがとう」っていう音など。音、文字?人間だけではなく、犬だったら?ということで、尻尾をつけた。つまり、動物の「ありがとう」。これなら、人目でわかる。これも、観察した結果。身の回りにヒントがある。そして、「ありがとう」とは言葉だけではない。身の回りを見てみると愛犬でもしている。車に尻尾をつける。エコグッズを作るときに、身の回りを観察し、大胆に置き換えてみる。
さとうりさのオブジェ。塩化ビニルは、300~500度で燃焼するが、不完全燃焼でダイオキシンを作る。燃やすことが出来ないのであれば、捨てられないものを作る。
(他のオブジェ)養蜂学に基づいており、実際にはちを飼っている。蜜源を探したりなど、活動が行われている。 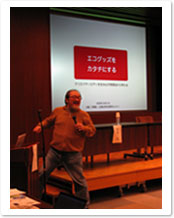
素晴らしいエコグッズとは、人の行動を変革する契機となる、商品やサービスなどのこと。
オーストリアにあるアートで、現代アートのオリンピックに出展されたものを紹介する。マケドニア紛争により、難民学校で使う言語学校、自立を促すための学校がアート作品である。これは未完成ですとし、実は難民キャンプで使われて初めてのものだが、皆さん参加しませんか、と実際に、難民キャンプを作ってしまった。これはアートなので、政治的介入も受けない。エコグッズとは関連無いかもしれないが、すごいエコグッズを作りましょう、は面白くない。人が参加しましょう、作品作りに参加しましょう、となると衝撃が薄くなる。
特に、観察することが大事である。
まとめ
大学で環境に関わる人、山口さん、そして中西さんからは発想をもらった。1500円ぐらいで売れるようなもの、つまり制作費だけかかっているもの。これを使うことが大学全体、あるいは地域の意識を促すというものであればいいのではないか。 |