|
<ESDRC教材シリーズ> |
|
*今後の参考にさせていただきたく、資料をダウンロードされた際には、
こちらのダウンロードフォームにてご感想等をお聞かせいただければ幸いです。(随意)
|
|
【ESD・開発教育教材 英訳版ダウンロードコーナー】
ESD研究センターでは、ESD・開発教育教材を広くアジア地域を含めた国内外へ紹介することを目的として、教材の英訳に取り組んでいます。日本語教材はいずれも、NPO法人開発教育協会(DEAR)において開発・普及されているもので、日本語の版権はDEARにあります。英語版作成にあたり、DEARに多大なるご協力をいただきました。英語版は自由にダウンロードしていただけますが、ご使用にあたりご感想、成果などをお寄せいただき、今後の参考にさせていただきたいと思います。ぜひご協力をお願いいたします。
連絡先:上條直美(kamijo@rikkyo.ac.jp)
【教材リスト】
If the World were a Village of 100 people- Workshop Edition
(『世界がもし100人の村だったら』)
Talk for Peace! : Let’s talk more what we can do to build up peace
(『もっと話そう! 平和を築くためにできること』)
The other side of the coffee cup
(『コーヒーカップの向こう側 貿易が貧困をつくる!?』)
"Poverty" and "Development" – Empowerment for better life-
(『貧困と開発 豊かさへのエンパワメント』)
Let's Visit the World of the Curry!! Diversity of Spices and Food Cultures 【付録】
(『たずねてみよう!カレーの世界 スパイスと食文化の多様性』)
The Palm Oil Story 【付録:写真、紙芝居】
(『パーム油のはなし~「地球にやさしい」ってなんだろう?』)
Thinking about "Development Aid"
(『援助する前に考えよう』)
The life of a CellPhone : learning about how the world and we are connected
(『ケータイの一生 ケータイを通して知る 私と世界のつながり』)
ESD for the Young 【表紙】
(『若者のためのESD』)
【日本語版問い合わせ先】
NPO法人 開発教育協会 http://www.dear.or.jp/ (教材・出版物の一覧がご覧いただけます)
|
|
|
|
 |
|
|
 |
|
|
|
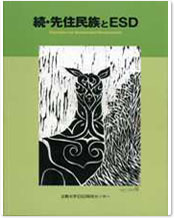 2011年度 ESD研究センター発行 2011年度 ESD研究センター発行
ESD教材集
『続・先住民族とESD』
好評であった『先住民族とESD』の続編です。小学生にも実施できる教材として「あんな服こんな服」「シコツの500年」を収録しました。先住民族とアイヌをめぐる課題を理解するためぜひご活用ください。
■目次■
はじめに 阿部治
解説 先住民族をめぐる課題とESD教材 田中治彦
教材1 あんな服こんな服 樋口歩
教材2 シコツの500年 渡邉圭
コメント みんなが描く未来 砂澤嘉代
*本教材は、PDF版で提供しています。
ダウンロードはこちら→『続・先住民族とESD』 【表紙】 【付録】 【地図A】 【地図B】
|
|
|
|
|
 |
|
| 
|
|
|
|
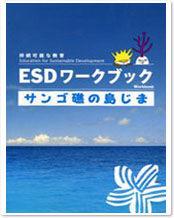 2011年度 ESD研究センター発行 2011年度 ESD研究センター発行
ESD教材集
『ESDワークブック サンゴ礁の島々』
サンゴ礁の島じまには、サンゴの破壊や廃棄物、地球温暖化など生活や産業などに伴う様々な問題があり、このままでは暮らし続けることが困難になってしまいます。このような事態を解決していくためには、個々の問題どおしのつながりを理解し、総合的に取り組むことが必要です。持続可能な社会をめざして問題解決に主体的に取り組む人々を育てる活動は持続可能な開発のための教育(ESD)とよばれており、国連は2005年からESDの10年として世界中で取り組んでいます。本書は、サンゴ礁を題材とするESD教材として、立教大学ESD研究センターが作成しました。是非ご活用下さい。日本語版(PDF)
*当教材は、2011年度に作成された“ESD Workbook Coral Reef Islands”の日本語版です。
英語版はこちら→ 英語版(PDF)
|
|
|
|
 |
|
|
|
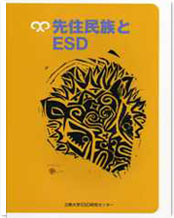 2010年度 ESD研究センター発行 2010年度 ESD研究センター発行
ESD教材集
『先住民族とESD』
世界各地の先住民族は近代化の過程で、もっていた土地や権利を奪われ、民族的な差別を受けて固有の文化を失いつつあります。日本においても1997年にアイヌ文化振興法が成立し、また2008年には衆参両院で「アイヌ民族を先住民族とすることを求める決議」がなされるなど一定の動きがあります。本書では、先住民族が置かれてきた歴史的な立場を理解するための参加型教材「ティフ星人はパセリを食る」を紹介するとともに、アイヌ民族の課題に関する資料集を掲載しました。先住民族とアイヌをめぐる課題を理解する教材として活用してください。
【目次紹介】
はじめに
解説
1 先住民族をめぐる課題と教材作成
2 先住民族に関する国際的動向
3 アイヌ民族と土地―旭川のアイヌから
教材「ティフ星人はパセリを食べる」
1 ティフ星人がやってきた!
2 史実カード
Ⅰ北海道(アイヌ民族)
Ⅱマレーシア・サラワク州(イバンなどの先住民族)
3 私の願い
4 アイス・ブレイキング
①こんな人を探してみよう
②進化ジャンケン
③映画トーク
資料
1 北海道旧土人保護法
2 アイヌ民族に関する法律(案)
3 アイヌ文化振興法
4 先住民族の権利に関する国際連合宣言
5 参考文献
*本書はPDF版で提供しています。ダウンロードはこちら→『先住民族とESD』 【表紙】 【表紙裏】 |
|
|
|
 |
|
|
|
|
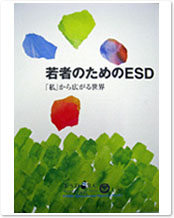 2009年度 ESD研究センター発行 2009年度 ESD研究センター発行
ESD教材集
『若者のためのESD-「私」から広がる世界-』 (第2刷)
グローバリゼーションにより孤立化しつつある「自分」の位置を、社会と世界の中で明らかにし、自分が社会や世界とどう関っていけるのかを考えます。また、自分の将来について、自身の過去と現在に照らして考えることにより、自分の将来の職業や人生について想像します。開発教育や環境教育の前段階として、あるいはキャリア教育の教材としても活用できます。
【目次紹介】
はじめに
本書の目的と使い方
1. ものローグ
2. 私って何?― つながりの中の自分
3. 原風景マップ ― 子どもの頃の私
●解説1 青年期の成長と発達
4. グローバル・ビンゴ ― こんな人を探そう
5. ケータイで広がる世界 ― モノを通した世界のつながり
6. リーマン・ブラザーズが破壊した!
●解説2 グローバル化する社会と開発教育
7. みよし町中華街構想 ― 多文化社会に生きる
8. 私たちのまちづくり
9. もし地球の気温が2度上がったら ―共通の未来を考える
●解説3 持続可能な社会とESD
10. 30歳の私
11. 私の近未来
●解説4 不確実な未来を生きる
※本書の頒布は終了いたしました。
|
|
|
|
 |
|
|
|
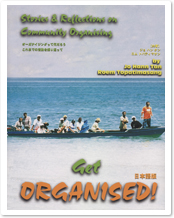 2007年度 ESD研究センター発行 2007年度 ESD研究センター発行
コミュニティ・オーガナイザー向けハンドブック
『Get Organized!』 (日本語版)
【紹介】
本ハンドブックは、東南アジア各地で活動するコミュニティ・オーガナイザーのネットワーク団体であるSEAPCP(South East Asia Popular Communications Programme)が2003年に発行したハンドブック”Get Organized!”の日本語版です。
(特活)開発教育協会と立教大学ESD研究センターの共同発行に際しては、SEAPCPの多大なるご協力を賜りました。
本書では、コミュニティ・オーガナイジングの枠組みや、東南アジア各国の実践事例などが紹介されています。先住民、小農民や零細漁民、都市貧困者、暴力の被害者である女性などが主体となり、自らの状況を変えていく取り組みが紹介されており、貧困や環境破壊、人権侵害などの当事者自身が問題解決をする過程で、学習や参加のプロセスを学び、より持続可能な社会を作る力をつけていきます。そのプロセスをどのように進めていくか、コミュニティ・オーガナイザーの役割とは何か、ということが改めて本書の中で整理されています。
日本の地域におけるESDの普及推進を目的として、地域の福祉、まちづくり、平和・差別などさまざまな分野の現場で活動する人々と共有できるハンドブックとして活用されることを期待しています。
■内容紹介■
はじめに
コミュニティへのアプローチ
コミュニティへのファシリテーション
戦略を立てる
集団行動のためにモチベーションを高める
団体のシステムと仕組み
サポートサービス
おわりに
参考文献・資料
■原著:執筆者■
ジョ ハン タン (Jo Hann, Tan) マレーシア
1986年、フィリピン大学でマス・コミュニケーション(ジャーナリズム)を専攻。1991年、東南アジア諸国のコミュニティ・オーガナイザーらと共に、東南アジア地域の草の根運動のネットワークである東南アジア大衆コミュニケーションプログラム(SEAPCP)を創設。1993年にマレーシアに帰国し、プサット・コマスを設立し、コミュニティとNGOをサポートする独創的な手法を提供している。
ロム トパティマサン (Roem Topatimasang) インドネシア
インドネシア東部スラウェシ島の村に生まれる。バンドン教育大学で教育哲学と教育計画を学び、70年代の学生運動全盛の中で過ごす。コンサルタント、トレーナー、リサーチャーの才能を活かし、ジャカルタやバンドンなどインドネシア各地で積極的にNGO活動に従事。草の根コミュニティの考え方の向上、人権、人々が力をつけていく過程に関する記事などを執筆。ドキュメンタリービデオの制作にも関わる。
※本書の頒布は終了いたしました。
|
|
|
|
 |
|
|
|
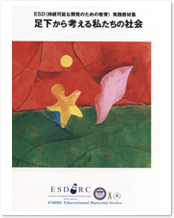 2007年度 ESD研究センター発行 2007年度 ESD研究センター発行
ESD教材ハンドブック
『ESD(持続可能な開発のための教育)実践教材集 足下から考える私たちの社会』
【紹介】
ESD教材ハンドブックは、(財)日本クリスチャンアカデミー関西セミナーハウス活動センター 開発教育研究会 に業務委託し、編集・制作されました。
本書では、人権、環境、平和、貧困、多文化共生、公正な社会、ライフスタイル、市民参加、内発的発展の9つの課題分野が統合的に教材の中に織り込まれ、私たちの社会を多角的に捉える視点を提供しています。日本国内における足下の開発問題に気づき、当事者としてそれらの課題に取り組む市民参加の視点を重視しつつ、「日本の中の持続不可能な問題」を問う必然性、重要性を提示しています。
日本におけるESDの普及推進を目的とした学習教材、学習プログラムの提案を行い、学校現場のみならず広く社会の各分野においてESDを普及推進していくことに活用されることを期待しています。
■目次紹介■
序文 なぜ「足元から考える」のか
教材と課題分野の対照表(マトリックス)
基本アクティビティの説明
第1章 人とくらし:コミュニティのありようをみつめて
教材1 なんでも?!100円ショップ:100円ショップから世界を考える
教材2 コンビニから考える私たちのくらし
教材3 参加型開発の手法を取り入れたまちづくり
第2章 人と生き方:多文化共生をめざして
教材4 食卓の牛肉から見える世界
教材5 “ホームレス”ってどんなひと:一緒に考えよう!野宿者問題
教材6 「多みんぞくニホン」を生きる
第3章 未来にむけて:平和な社会を築いていくために
教材7 核と温暖化:マーシャルと日本
教材8 沖縄から考える平和
※本書の頒布は終了いたしました。
→本書の教材の一部が次の書物に収録されています。
開発教育研究会編『身近なことから世界と私を考える授業』(明石書店、2009年)
|
|
|
 |
|
|
|
↑ページトップへ |
|
|
|